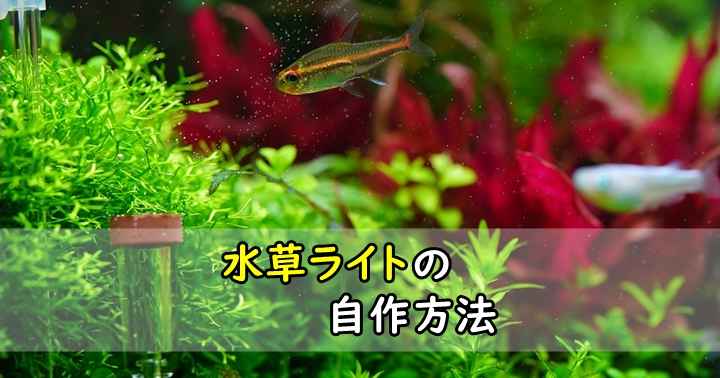爬虫類のエサになる虫の種類。ショップで販売している虫から、その辺で捕まえられる虫まで
国内・海外の種類問わず、爬虫類が何を食べるのかイマイチわからない人もいると思います。
種類によっては食性も変わり、人工餌でも食べる種類もいれば、生きている餌しかなかなか食べない種類も。
はては果物だって食べるものもいます。
今回は爬虫類がしっかり食べてくれる、昆虫などの餌の紹介をします。
食いつきが良いのは「活餌」
どんな爬虫類でも食べてくれるのが、生きた虫などの「活餌」です。
リクガメのような草食性の爬虫類でもなければ、まず間違いなく食べてくれるエサといえるでしょう。
自然と生きている=害がないと判断してくれるため、動かない餌よりも食いつきはいいです。
爬虫類飼育が初めての人は特にそうですが、安定して食べ続けてもらいたいなら優先的に与えていきましょう。
市販されている活餌にもかなりの種類があり、各活餌の特徴がこちら。
| 栄養 | 取り扱い | 自家繁殖 | |
|---|---|---|---|
| コオロギ | 〇 | 〇 | ◎ |
| ミルワーム | △ | ◎ | × |
| ゴキブリ | 〇 | △ | ◎(※) |
ただ、それぞれにも種類がおり、扱い方も変わってきます。
特に自宅でキープするために保管しようと考えている人は、虫の特徴をよく覚えておきましょう。
コオロギ
かなりメジャーな活餌で、大抵の爬虫類はしっかり食べてくれます。
一般的に市販されているコオロギの種類には「ヨーロッパイエコオロギ」と「フタホシコオロギ」があります。
「扱いやすいヨーロッパイエコオロギ」「量のフタホシコオロギ」と覚えられます。
ヨーロッパイエコオロギ
「ヨーロッパイエコオロギ」(以下イエコオロギ)は少々小さめのコオロギです。
その分小さい個体でも食べられるサイズなので、幼体から育てても安心して与えられます。
少々名前が長いのでショップなどでは省略されて「イエコ」なんて呼ばれたりもします。
後述する「フタホシコオロギ」ほど臭いもないです。
自宅で繁殖させたりキープするのにも抵抗は少ないと思います。
ただ生体になっても1.5~2cmくらいまでしか成長しません。
そのため爬虫類のサイズが30~40cmを超える個体になると、少々物足りないと感じるでしょう。
コオロギは草食寄りなので、キープ・自家繁殖させる際には野菜クズといったものを与えていきましょう。
コオロギ専用のエサも売っているので、栄養価を上げたいなら使うのもいいと思います。
フタホシコオロギ
「フタホシコオロギ」は少々大きめのサイズ、それこそ生体なら3cmほどとイエコオロギの倍くらいの大きさになります。
大きい分食べ応えがあり、爬虫類が30cmくらいのサイズなら2~3匹くらい与えればおなかもかなり膨れます。
50cmくらいまでは大丈夫なので、1m越えのような爬虫類でもなければお腹を空かせることもないと思います。
ただ臭いがキツイため、余ったコオロギをキープしたり、繁殖させるときには注意してください。
特に死んだフタホシコオロギはかなり臭うので死骸は早めに処理しましょう。
個人的に自家繁殖させるならイエコオロギの方が臭いも少なくオススメです。
保存用コオロギ
上記のコオロギを乾燥・冷凍・缶詰めなどにして長く保存しやすくしてあるものです。
生きてはいませんが冷蔵庫などで保存できるため、管理の手間は省けます。
ただ生きていない分、食べてくれる頻度も減ってしまいます。
特に缶詰めのコオロギは臭いが少々キツクなっているので、開封したら早めに与え切ってしまいたいところです。
ミルワーム
ミルワームも代表的な活餌になります。
おそらく「生きているエサ」の中では特に保存がラクな部類に入ると思います。
ミルワームにも種類があり、2~3cmくらいの一般的なミルワームと、5cmくらいの「ジャイアントミルワーム」があります。
ジャイアントミルワームの方が食べごたえもあるため、サイズが大きい個体ならこちらを与えましょう。
キープも簡単で、カブトムシなどの昆虫用マットにいれておけばOK。
野菜クズなどを入れておけば良いので、ミルワームの餌にも困りません。
ただ自家繁殖は非常に難しいです。
普段目にしているミルワームは幼虫で、生体はカナブンやコガネムシのような形態になります。
そして卵を産ませてようやく、といった具合で、与えられるまでの期間が非常に長いです。
生体のミルワーム(ワーム…?)は自己防衛のためにクサい臭いを出します。
この臭いのせいで食いつきが悪く、餌としては向いていません。
生体に成長させたくないなら冷蔵庫で保管しましょう。
冷たい環境だと冬眠状態になるため、食べにくい生体になるのを防げます。
基本はワームのままキープし、買ってきた分は早めに与え切ってしまいましょう。
注意点として、ミルワームは栄養の偏りがあるため、ミルワームだけ与えていると栄養が足りなくなる恐れがあります。
即座に影響は出ませんが、ミルワームばかり与えていると生育不良が出ることも。
他の活餌と併用したり、後述する爬虫類用のサプリメント「栄養パウダー」をふりかけたりして栄養価を高くしましょう。
餌用ゴキブリ
爬虫類のエサとして専用の「ゴキブリ」もいます。
…「ゴキ」と聞くと抵抗が強い人も多いでしょうが、「チャバネ」と違って餌としての種類のゴキブリになります。
そんな違わないと思う人も、これまた多いでしょうが…。
有名なものとして「デュビア」と「レッドローチ」という種類のゴキがいます。
こちらもコオロギの「イエコ」と「フタホシ」のように、真逆の生態をしています。
もし餌として使うなら、自分に向いたほうを使いましょう。
デュビア
黒く大きめのゴキで、正式名称は「アルゼンチンフォレストローチ」といいます。
「フォレスト」の通り森に生息しているゴキです。
動きが緩慢な(のそのそ動く)ため簡単に捕まえられるので、コオロギと違ってトカゲに与える際の時間や手間を減らせます。
ボリュームもあり生体は4cmくらいまで成長します。
そのため50cm越えの爬虫類でも主要な餌として与え続けることができます。
他のゴキにもいえますが意外と臭いが少ないです。
コオロギほどの臭いがしないため、キープや繁殖の際の臭いによる不快感を減らせます。
プラケースのようなツルツルの壁は登れないので、脱走の危険性は少ないです。
ただよく「飛ばない」なんて聞きますが、羽根があるオスのデュビアではホバリングくらいはします。
ケースの高さによっては脱走しかねないので注意してください。
ただ繁殖力は低めです。
ペットを多く飼っていたり、たくさん与えていると供給が追い付かなくなるので覚えておきましょう。
レッドローチ
レッドローチは名前の通り赤い色をしたゴキで、デュビアと正反対の特徴を多く持っています。
まずデュビアと違い小さめのサイズで、30cm以下の小型の爬虫類向きのエサといえます。
しかし繁殖力が強く短期間で増えるため、自家繁殖させるのは容易です。
臭いはデュビア同様少ないためそこまで気にすることは無いと思います。
ただ動きが少々早くなるので捕まえる手間はその分増えます。
また成長すると壁を登れなくなりますが、幼体のように軽いと登る個体もいます。
デュビアよりも小さい=身体が軽いので、ホバリングの距離なども伸びるのでより注意してください。
※ゴキを繁殖させる際の特大の注意点
「デュビア」にしても「レッドローチ」にしても、「ゴキ」が脱走するのだけは防ぎたいでしょう。
そのため「登りにくいツルツルなプラケースを使う」「洗うときにケースにキズをつけない」。
これだけは特に注意して管理しましょう。
これらのゴキは壁を登る能力が低く、特に成長すると自重で登れなくなるくらいです。
しかしケーズの壁に少しのキズや汚れがついていると、そこに足を掛けて登ってきます。
脱走する場合はこれが多いです。
そのためケースを洗うときは、布のような柔らかくキズをつけないもので洗うようにしましょう。
スポンジで洗うと微細なキズがつくので、小さいゴキだとより登りやすくなります。
とにかく壁を登っての脱走を防ぐには「ケースの壁はできるだけキレイにしておく」「壁にキズがつかないように洗う」。
これらを順守して管理するようにしましょう。
冷凍○○
活餌とは少々違いますが「生(ナマ)」ということで紹介します。
・冷凍ヒヨコ
主にヘビや「オオトカゲ」などの大きいトカゲのエサになります。
よほど専門的なショップでないと取り扱ってない場合があるので、ネットショップなどで取り寄せるしかありません。
しかし本当に1m越えのような大型の爬虫類に与えるエサです。
それより小さい爬虫類なら他のエサで代用したほうがラクですし、コストもかかりません。
「冷凍」の通り普段は冷凍庫などで保存します。
他の食材と混ざるのがイヤなら、専用のスペースを確保してから購入しましょう。
その他:庭などで捕まえられる虫
ここからは庭先などで捕まえられる虫で、かつトカゲが食べてくれるものを紹介します。
とはいっても、大抵の虫なら食べてくれますが。
ただ毎日のように与えるのは難しいと思うので、緊急用や数回分のエサ代が浮くくらいに考えましょう。
バッタ
主のメジャーな種類の「バッタ」も、コオロギと同じくよく食べてくれます。
ただ「バッタ」といっても2cmくらいまでしか成長しないものや、トノサマバッタのように10cm近く成長するものもいたりします。
しかもバッタは細長いため、コオロギのように一呑みにできないことが多いです。
特に大きな後ろ足がついているバッタだと、その足が食べるのに邪魔になってきます。
あらかじめ後ろ足を取っておけば食べやすいですし、ジャンプなどもできなくなるので脱走の心配も減ります。
エンマコオロギ
エンマコオロギは日本に生息しているコオロギで、普段庭などで見るのはこの種類になります。
エンマコオロギも「イエコ」や「フタホシコオロギ」のように好物なので、同じようによく食べてくれます。
ただエンマコオロギはこれらのコオロギより大きく・固くなります。
30cm以下の爬虫類だと食べづらそうにすることが多いです。
小型の爬虫類に成長しきったエンマコオロギを与えるときは、のどに詰まらせないように注意しておきましょう。
ミミズ
土の中にいるミミズもトカゲは食べてくれます。
小さいミミズなら数cmなので小型の爬虫類でも食べられます。
ただミミズは細長いため、バッタ以上に一呑みにするのは難しいです。
あまりにも食べにくそうなら1サイズ小さいミミズを与えるか、(作業がキツイと思いますが)半分ほどにちぎってから与えてみましょう。
しかしミミズは、長さの割に体積(肉の量)は少ないです。
おまけに栄養の偏りもあるようで。あまり餌には向かないとも。
ついでに土壌の汚染があると、餌にした爬虫類に悪影響が出ます。
例えば洗浄した車の下の土、あるいは農薬を多く使った畑など。
こうした場所で取ったミミズは与えないようにしましょう。
ちなみに自家繁殖させたいなら「シマミミズ」という品種のミミズがおすすめ。
このミミズは1~2か月もあれば数倍に繁殖するので、数の確保がしやすいです。
我が家ではもっぱらミミズコンポストで使ってます。
その辺にいるミミズは「フトミミズ(ドバミミズ)」といわれ、大きくはなりますが繁殖力は低いです。
シマミミズは釣具店やミミズコンポストのミミズとして販売しています。
確実なのはミミズコンポストの方なので、興味がある人はそちらを購入しましょう。
ダンゴムシ
自然の中ならどんな場所でもいるのがダンゴムシです。
バッタやミミズ以上に捕まえやすい虫だと思います。
ただかなり小さく、「ニホントカゲ」や「カナヘビ」のようなかなり小さい爬虫類に限られます。
食べてはくれますが、餌としての重要度は少ないでしょう。
ミルワームと同じく栄養が偏っているので、ダンゴムシだけを与えるのも栄養上マズイです。
本当に小さいトカゲや、幼体の爬虫類のみに与えることになると思います。
「カナブン」や「コガネムシ」の幼虫
畑やプランターの土を掘ると、偶にいる「カナブン」や「コガネムシ」の幼虫も餌になります。
子供の頃「カブトムシの幼虫だ!」なんて間違えた人も多いと思います。
これらの幼虫ですが、栄養価はかなり高いです。
テレビのサバイバル的な内容の番組で、カブトムシの幼虫みないなのが「たんぱく質などの栄養が豊富!」なんて感じで紹介されているのと同じです。
一応簡単にそれぞれ紹介します。
詳しい見分け方などを知りたい人は別途記事にまとめてあるので参考にしてください。
コガネムシの幼虫

コガネムシの幼虫は農家の人に言わせれば「害虫」です。
こいつは植物の根を食べて、野菜や果樹がいきなり枯れる原因のひとつになってます。
大きな特徴は、頭が大きく地面を這って歩きます。
私は趣味で家庭菜園をしていますが、秋の初めや春先に土の整理をしているとこいつが大量にいたりします。
まあそんなときは飼ってるトカゲに軒並み与えているので、「餌が増えてラッキー!」なんて思ってますが。
コガネムシの幼虫は「生きた」植物の根を食べているため、キープしておくのは難しいです。
もし見つけたら早めに与えてしまいましょう。
カナブンの幼虫

カナブンの幼虫は腐った植物をエサにしているので、大量の落葉や枯れ草の下にいることが多いです。
コガネムシの幼虫に比べると頭がかなり小さく、背中を動かして仰向けのまま歩き(?)ます。
身体もプックリしているので、エサとして食べごたえも増えてます。
カナブンの幼虫は植物の根を食べずに腐ったものを食べるため、率先して駆除する必要はあまりありません。
腐ったものを優先的に食べるため、落葉や野菜クズなどを土に入れれば長時間キープすることができます。
もし大量に見つけたらキープしておいて、必要になった分だけ与える、といったことも可能です。
活餌を与えるときは「サプリメント」を併用すべし
トカゲは活餌をよく食べてくれますが、エサによって栄養価にはかなりバラつきがでます。
例えばミルワームなどはそれが顕著です。
ミルワームは身体がチキン質で出来ているため、栄養の主成分もそれに順守してしまいます。
そうなると他に必要な栄養が摂取できなくなるため、爬虫類の健康上もよろしくないです。
そんなときは、どんなエサでも栄養価を高くしてくれる爬虫類用の「サプリメント」を使いましょう。
このサプリメントはパウダー状になっており、エサに振りかけて使います。
ウロコなどを作る栄養素の「カルシウム」をメインに、ビタミンなども含んでいるため、どんなエサでも栄養価を高くできます。
一種類の活餌ばかり与えていると摂取できる栄養も偏りやすいです。
サプリメントを併用してエサの栄養価を高めてから与えるようにしましょう。
餌のキープも意外と大変
こんな感じで、トカゲが食べてくれる「活餌」の紹介を終わります。
いきなり多種類の活餌に手を出すと管理が大変です。
特に数日間だけのキープでも、慣れてないとすぐに死んでしまいます。
冷凍○○は保管はラクですが、他の餌に比べてかなり高コストです。
初心者の人はまず入手(購入)が容易で、(外見的)ハードルが少ないミルワームやコオロギから始めてみましょう。
物足りなくなってきたら他の活餌も検討してみる、くらいでも大丈夫です。
ペットが活餌にがっついてる姿を見ると元気にしていると安心できます。
爬虫類の飼育初心者の人なら、まずは安定して食べてくれる活餌を与えてみましょう。