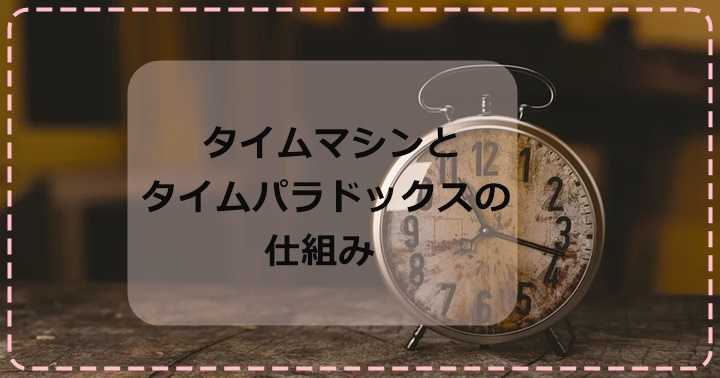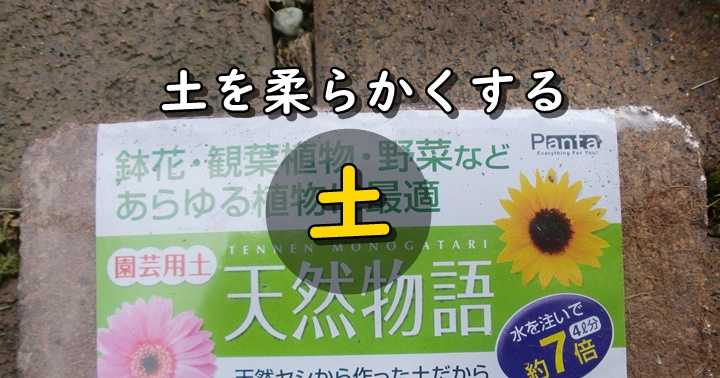畑やプランターで出てくるカブトムシっぽい幼虫の正体。種類によっては作物に害も
畑などで土を掘っていると、たまにカブトムシの幼虫っぽいのが出てきます。
しかしカブトムシの幼虫にしては小さく、見慣れてくると微妙に違う形をしてるのが分かると思います。
幼虫は2種類ほどおり、どちらがどう作物に影響・害があるのかわからない人もいると思います。
この幼虫の正体は一体何なのか、作物に害はあるのか等を解説します。
正体
この幼虫の正体は「カナブン」か「コガネムシ」の幼虫になります。
カブトムシやクワガタの幼虫じゃありません。
そもそもカブトムシなどの幼虫は朽木(枯れて倒れた木)のボロボロとなった部分を食べます。
畑の土を食べることはありません。
たい肥などでも同じです。
大きさも段違いで、これらの幼虫は直径(丸まった状態)が精々2~3cmほど。
しかしカブトムシの幼虫は5cm近くあります。
カナブンやコガネムシの幼虫は同じように見えますが、よくみると明確な違いがいくつもあります。
花や作物に害があるかどうかも含めて、これから解説したいと思います。
コガネムシの幼虫

作物に害あり
ますコガネムシの幼虫ですが、こいつは作物などに害があります。
コガネムシの幼虫は主に作物の根を食べます。
放っておくとどんどん根を食べられて、あっという間に作物が枯れてしまいます。
特に大根や人参・芋といった野菜だと被害は大きくなります。
樹木などの根っこでも同じで、果樹栽培でも油断できません。
長年育てた果樹がいきなり枯れた場合は、このコガネムシの幼虫が根をかじり尽くしていることもあります。
酷いときは3mくらいあった樹を少し上に引っ張っただけで抜けてしまう場合も。
強めの風邪が吹いただけで樹が根本から傾いてしまうことも。
プランター栽培だと根っこが密集して量も少ないため、コガネムシの幼虫の被害が大きくなる傾向にあります。
区別の仕方
コガネムシの見た目で判断するには、この部分を見てみましょう。
・胴体が細い
・歩き方が四つん這い
・退職が黄色い場合も
・栽培中の畑で見る
後述するカナブンの幼虫と判別するには、これらを見るとわかりやすいです。
①頭(アゴ)が大きい
根っこをかじれるように発達しているため、頭やアゴが大きいです。
後述するカナブンの幼虫が申し訳ない程度にしかないのに対し、数倍ほどの大きさがあります。
土に潜るときにアゴで掘ったりするためか、手に乗せていると噛みついてきます。
手に乗せて噛みつかれた場合はコガネムシの幼虫の可能性が高いです。
②胴体が細長い
カナブンの幼虫に比べるとほっそりした体形をしています。
胴体部分が少し平べったく、太っているような印象は受けません。
丸まったときに真ん中部分に隙間ができるくらい痩せてる(?)ことも多いので、こちらでも判別しやすいです。
③四つん這いで歩く
ダンゴムシのようにしっかりと自分の足で歩きます。
最初は丸まっていても、すぐに土を掘って逃げようと歩き出します。
ただ少し歩きづらいのか、自分のお尻部分を引きずって歩いている感じがします。
④黄色い体色の場合も
基本的に白の場合が多いですが、黄ばんだような体色の場合があります。
カナブンの幼虫は白以外にいません(少なくとも自分は見たことないです)
少しでも黄ばんだ色をしていたらコガネムシの幼虫でしょう。
⑤根がある所で見かける
食べる対象が生きた根っこなので、作物を栽培中の畑の土で見かけることが多いです。
そのため栽培中の畑やプランターの土から幼虫が出たら、コガネムシの幼虫の可能性が高いです。
逆に栽培を終えて長い期間放置されている土ではエサが無いので、ほとんど見かけません。
放っておくと根が食べられてしまうので、その場で取り除きましょう。
カナブンの幼虫

特に害は無い
カナブンの幼虫には目立った害はありません。
カナブンの幼虫の食べるものは基本「腐ったもの」だけ。
そのため栽培中の作物付近ではあまり見かけません。
いたとしても腐ったものしか食べないため、成長している最中の作物にはあまり影響はありません。
収穫後の放置されている土だと残っていた根が腐ってくるので、それをエサにしていることが多いです。
「腐ったもの」がエサということで、たい肥などの中にもいることが多いです。
ただ芋のように土の中で育つ作物の場合、腐った部分が出てくるとそこを食べ始めたりします。
水のやりすぎだと腐ってしまうことがあるので、水の与えすぎには注意しましょう。
区別の仕方
カナブンの幼虫はコガネムシの幼虫とは正反対の特徴が多いです。
・太ってる
・足で歩かない
・放置された土で見る
両方見たことがあるなら、割とわかりやすい部類かと。
①頭(アゴ)が小さい
アゴが発達していないため、頭がかなり小さいです。
これは腐った(柔らかい)ものしか食べないためです。
写真を見比べてみるとよくわかります。
コガネムシの幼虫の頭は胴体の太さと同じくらい。
対して、カナブンの幼虫は胴体の先っちょに小さい赤い部分がついているだけな感じです。
アゴはほぼ無いといえるくらいで、手に乗せてもかじられることは稀なので危険は少ないです。
頭が小さいのを生かしてか、頭を動かして土をかき分けて潜っていきます。
②胴体が太い
カブトムシの幼虫のようにでっぷり太った感じの身体になってます。
違うのはサイズだけ。
コガネムシの幼虫に比べるとかなり太く、丸まったときにギュウギュウに詰まって隙間なく固まります。
丸くなると「正円」に近い形で、楕円型のカナブンと比べても見分けやすいです。
胴体の形状でも、カナブンの幼虫は頭からお尻に向かうにつれ太くなっていきます。
コガネムシの幼虫では胴体の太さが変わらないため、ここも見分けるポイントです。
※ちなみにカブトムシの幼虫は「胴体が均一に太い」という、コガネムシ・カナブンの幼虫両方の特徴です。
③背中で歩く
カナブンの幼虫は脚を使わず背中で歩きます。
脚は発達しておらず、自分で歩けないほどです。
そのためなのか地面の上を移動するときは自分のお腹を上にして、「背泳ぎ」ならぬ「背歩き」で移動します。
その異様な移動風景を少し気持ち悪いと感じる人もいるかと。
④たい肥の中で見かける
先述した通りカナブンの幼虫は腐ったものが主食。
そのため、たい肥などの中で見かけることが多いです。
特に枯れ葉を集めた場所や、作物を収穫した後に放置された土の中でよく見かけます。
どちらかというとミミズの生態に近いです。
ミミズがたくさんいる場所だと生息に適していたりします。
防ぎ方
カナブンはともかくコガネムシの幼虫は明確な害があるので、できれば防ぎたいのが実情です。
その防ぎ方ですが、土の上をシートなどで覆うくらいしか手がありません。
土がむき出しだと成虫が土の中に卵を産み付けやすい状態です。
なので、できるだけ土に触れないような環境にする必要があります。
石や大き目の木のチップなどで土の表面を覆っても効果はあります。
あまり植物にいい環境とはいえませんが、掘れないほど固くなった土でも産み付けは困難になります。
こうした方法でシーズン中に卵を産み付けられる可能性を低くできます。
コガネムシの幼虫の見つけ方
コガネムシにしろカナブンにしろ幼虫の見つけ方はあります。
が、経験上かなり難しく、後手に回ることが多いです。
特にコガネムシの幼虫の見つけ方を参考程度に書いておきます。
急に枯れる・元気が無くなる
急に作物の元気が無くなるとコガネムシの幼虫がいる可能性が高いです。
作物の成長シーズンでこれが起きたら要注意です。
特に樹木に対する影響が大きく、太い根をかじられると急に枯れる事態になることもあります。
プランターで栽培していると根が密集しやすく、被害が大きくなりやすいです。
確かめる一番の方法は一度土ごと引っこ抜いて調べることです。
早くに除去できればまた成長してくれます、
手遅れになる前に見つけ出しましょう。
樹がいきなり傾く・抜ける
果樹などが根元から急に傾いたり、抜けてしまったりすることがあります。
春先に植えた果樹が順調に成長していたのに、ある日突然傾いた状態になっていたことがあります。
風が強い日があったため「強風で倒れたのか?」とも思いました。
が、植え直そうとしたら根っこがほとんどありませんでした。
調べてみるとコガネムシの幼虫が10数匹ほどいたため、念入りに調べて取り除きました。
数匹の幼虫でもかなりの被害が出ます。
異常を感じたらすぐに調べたほうがいいです。
一部の土の表面が柔らかい
周りに比べ一部分だけ土が柔らかかったら、そこに卵が産み付けられた可能性があります。
成虫が卵を産むには土を掘り返して産み付けます。
そのため掘り返された分、土が盛り上がって柔らかくなります。
幼虫が土の表面近くで活動していると土が耕されるため、そちらの場合もあります。
周囲に比べ、異様に土が柔らかかったら幼虫がいることも考えましょう。
フンが溜まっている
土の上に幼虫のフンが溜まっていることがあります。
コガネムシやカナブンの幼虫は黒っぽいフンを大量に出します。
土の表面近くで生活している幼虫が土の上に押し出す形でフンを出すことがあります。
規則正しい形をした土粒っぽいものがたくさんあったら、その下に幼虫がいる可能性があります。
石の下に陣取ることも
土の上に大き目の石や木を置いておくと、その下に幼虫が陣取ることがります。
これは雨宿りの代わりです。
頑丈な石などの下は雨水を通さないので、そこに避難する傾向にあります。
ただかなり深いところに常駐する幼虫もいるため「いたらラッキー」程度に思いましょう。
1匹いたらたくさんいる
一度にたくさんの卵を産むため、1匹いたら10匹くらいいる場合もあります。
そのため1匹捕まえたら、近くをできるだけ掘り返して探しましょう。
探す場所の目安としてはこうなります。
・カナブンの幼虫…比較的バラバラな位置
コガネムシの幼虫は生きた植物の根を食べるため、その周辺を。
カナブンは腐ったものを食べるため、そういったものが多い場所を探しましょう。
ただプランターなどで樹木を育てるとその内側に入り込むことがあるので、探すのはかなり困難です。
やはりシートなどで予防するのが一番です。
ただカナブンの幼虫は根を食べることも無いため、そこまで焦る必要はないと思います。
繁殖シーズンも収穫後のことが多いのも理由です。
片方だけいることが多い
体感ですが、片方一種類しか見かけないことが多い気はします。
私はプランター栽培が多いですが、一つのプランターに一種類だけいるパターンです。
カナブンを見かけたらカナブンだけ。
コガネムシならコガネムシだけと、一極化する傾向にありました。
おそらくエサの関係です。
栽培・成長途中の植物が多いとコガネムシの幼虫が。
枯れた結果腐ったものが多い場所はカナブンの幼虫が成長しやすい。
こうしたことから自然と選別されていると思われます。
逆に言うと一方を見かけたら片一方はいない可能性が高いです。
害のあるコガネムシの幼虫を探すときの指針にはなると思います。
最後に
やはりコガネムシの幼虫の被害が馬鹿にならないほどヒドイです。
以前リンゴの木が急に枯れかけてしまったことがあります。
引っこ抜いて確かめたら根の中心部にコガネムシの幼虫が陣取ってたことがありました。
すぐに除去して植えなおしたらまた成長し始めたので、早くに対応すれば枯らさずに済みます。
幼虫の見分けの仕方を覚えて、コガネムシの幼虫を探せるようにしておきましょう。