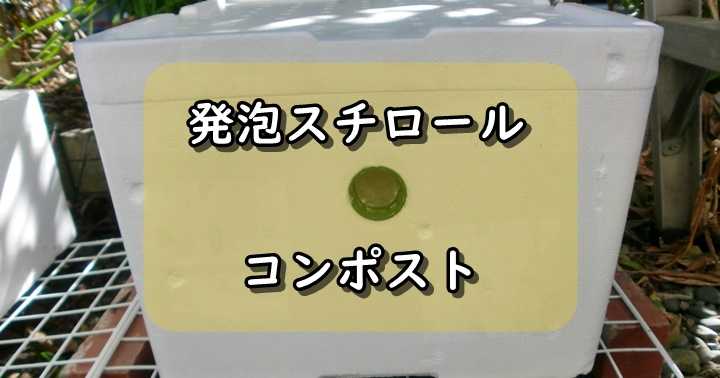生ゴミ堆肥を作るコンポストの種類。堆肥の作りやすさや手間の違いは?
生ゴミを処理するには、堆積型の「コンポスト」とミミズを使った「ミミズコンポスト」の2種類あります。
両方とも堆肥を作る方法ですが、堆肥のできるスピードや手間のかかりにくさなどには違いが出ます。
そのため「早く堆肥をつくりたい」。
あるいは「遅くてもいいからとにかく手間をかけたくない」なんて人もいると思います。
「コンポスト」と「ミミズコンポスト」では、どちらが・どの部分が優れているかなどを解説していきます。
コンポストの種類
堆肥作りで使えるコンポストには、大きく分けて3種類あります。
・大容量コンポスト
・ミミズコンポスト
屋内でも設置しやすい、持ち運びができる小型の堆積型コンポスト。
屋内に設置する、特大サイズの容器のコンポスト。
ミミズを使ったコンポスト。
この3つです。
機能性ならもっと細かいものはありますが、大きい分類はこうなります。
ただミミズを使ったコンポストは、すべてミミズコンポストとして分類します。
まずは、それぞれの特徴を簡単に表でまとめてみました。
| 家庭用コンポスト | コンポスト(屋外型) | ミミズコンポスト | |
|---|---|---|---|
| 処理速度 | 遅 | 遅 | 早 |
| 腐敗率 | 高 | 中 | 低 |
| 虫沸き | 中 | 高 | 低 |
| 液肥 | 回収 可 | 回収 不可 | 回収 可 |
私の主観や環境も関係しますが、大体こんな感じになるんじゃないかと。
しかし「堆肥を作り」という点においては、ミミズコンポストのほうが完全に優れています。
ある程度の手間は増えますが、失敗の要因を減らしたり堆肥を早く作るならミミズコンポストを使ったほうが良いです。
しかしミミズを使うのに抵抗がある人もいるでしょう。
それに室内では使いづらいので、生ゴミをイチイチ外に持っていくといった手間もあります。
生ゴミの腐敗さえ無くせれば、普通のコンポストのほうが使いやすいというメリットもあります。
家庭用の小型コンポスト
まずはコンポストでイメージするであろう、生ゴミを積み重ねて行うコンポスト。
こちらは持ち運び可能な、小型のコンポストの紹介になります。
ホームセンターでも扱っており、誰でもすぐに始められます。
通常コンポストの長所
普通のコンポストは生ゴミをそのままコンポストに投入するだけな感じ。
いくつか注意する点はありますが、後述のミミズコンポストほどあまり色々考えずに使えます。
・コンポストの購入のしやすさ
・コンポストの種類の多さ
このように、生ゴミ堆肥作りに参入する敷居がかなり低くなってます。
用意するものも最低限で済むのも特徴です。
一度の処理量が多い
通常のコンポストの一番の長所は一度に詰め込める生ゴミの量が多いのが挙げられます。
生ゴミの処理方法が「生ゴミを積み上げる」「投入する」だけ。
なのて、生ゴミが出たらどんどんコンポストに入れられます。
生ゴミが出たら、まるごとコンポストに入れることができるため、ゴミの量を少なくできます。
どんな生ゴミでも満遍なく処理できる
基本コンポストで生ゴミを処理する場合、微生物の働きによって分解され堆肥になります。
生ゴミの種類(固い・柔らかいなど)によっては分解時間に違いが出ますが、どんな生ゴミでもコンポストに投入できます。
後述のミミズコンポストと違い、生ゴミの分別をせずに済みます。
専用の容器が多数ある
多種多様のコンポスト容器があるため、簡単にコンポストで生ゴミ処理を始められます。
ホームセンターに行けば、大抵は1つ2つは置いてあると思います。
容器の大きさや、屋内でも使えるものと幅広い種類があるのも特徴。
自分に合ったどんな環境でも生ゴミ処理ができます。
液肥を回収できるように排水口がついているもの。
地面にそのまま置いて、どんどん生ゴミを入れられるデカいコンポストなど様々。
どんなコンポストにしても、臭い防止・排水機能などが付いているものが殆どです。
生ゴミ堆肥作りの初心者でも、前準備や使用方法の理解が容易に出来ます。
通常コンポストの欠点
堆積型のコンポストの欠点として目立つのが、堆肥になるスピードと失敗する要因の多さです。
手軽にできるのは確かですが、間違った方法を取ると失敗しやすいです。
・生ゴミの腐敗
・虫
堆肥になる時間はまだしも、腐敗や虫はかなりイヤでしょう。
取り扱いを間違えるとこうした失敗が増えます。
しかもどれか一つでも失敗すると、連鎖的に他の事態も引き起こしやすいのもマイナスです。
実際、私はこれらで失敗したことが多いです。
すぐに堆肥にならない
通常コンポストでは投入できる生ゴミの量は多くても、すぐに堆肥に変わるわけではありません。
季節にもよりますが、夏場など温かい季節なら2か月ほど。
冬場など寒い時期なら6か月ほどとかなり時間がかかります。
これは堆肥作りを完全に微生物頼りにしているのが理由。
微生物は温度が25~30℃くらいで活発に活動し、それより寒かったり暑かったりすると活動が鈍るか死滅してしまいます。
そのため四季のある日本では期間にバラつきが出ます。
すぐに堆肥が欲しい場合、堆肥を使う時期に合わせて堆肥作りをする必要があります。
生ゴミが腐敗しやすい
生ゴミの処理に時間がかかるため、投入した生ゴミが腐敗しやすいです。
微生物の活動が鈍る・水分が多すぎると、放置された生ゴミが腐敗しやすくなります。
生ゴミの水切りなどで水分量を調整すればある程度防げますが、それでも完全じゃありません。
腐敗にともない異臭が発生する可能性もあります。
こういったことから通常のコンポストでは「腐敗による失敗」が起きやすいです。
もし防ぎたいなら屋外用の地面に置いて使うコンポストを使いましょう。
こちらは余分な水分は順次抜けていくため、密閉された容器のコンポストのように腐敗は起きにくいです。
虫が沸く
上記の腐敗によって臭いが漏れたりすると、小バエなどの虫が出ることがあります。
少しでも臭いが漏れれば、どこからともなくやってきます。
腐敗に次ぐ失敗の原因になっています。
コンポスト内に入り込めばそこで増殖するため、失敗の原因のトップに位置します。
しかし、コンポストを完全に密閉することはできません。
密閉すると堆肥の発酵で出たガスによってフタが空いてしまいます。
これを防ぐために、弁付きの小さな空気穴が空いてます。
それでも完全には防げないのがネックです。
水が溜まりやすい
定期的に液肥を抜かないと腐敗や詰まる原因になります。
生ゴミというのはかなりの水分を持っており、堆肥に変わる過程で大量の液肥が出ます。
この液肥がコンポスト内に溜まりすぎると、水分多寡での生ゴミの腐敗や、排水口が詰まる原因になります。
投入している生ゴミの量や頻度にもよりますが、数日したら液肥を回収しましょう。
できればある程度乾燥させた生ゴミを投入するのがベストでしょう。
堆積型コンポスト(屋外型)
次に屋外に設置する、特大のコンポストについて。
通常の小型コンポストと似た特徴は多いですが、優れた部分もあります。
逆に省かれた部分もあるので注意。
屋外型コンポストの長所
長所部分は、通常のコンポストと共通してます。
それに加え、
・腐敗率の低下
この2つが追加されます。
生ゴミの処理量の増加
屋内にで使用できる、小型のコンポストの容量は精々20リットルほど。
しかし屋外設置専用のコンポストでは一度に100リットル以上処理できるものも多いです。
そのため大量の生ゴミが出る家庭や、堆肥をたくさん作るのに優れています。
これは単純に容器を大きくしたから。
またコンポストが黒色のため、太陽光で温度が上昇しやすいです。
コンポスト内の温度が上昇すれば微生物の活動も活発になります。
このため冬場でも堆肥作りがしやすくなってます。
こちらは生ゴミだけでなく、落ち葉や枯れ葉・収穫シーズンが終わった作物の残骸もジャンジャン入れられます。
毎年庭掃除で大量の落ち葉などが出る人にオススメです。
庭先にスペースがあるのなら、こちらのコンポストも使ってみましょう。
腐敗率の低下
コンポストの構造上、地面に被せるタイプのものが多いです。
そのため腐敗の原因となる水分が地面に染み込んで無くなっていきます。
これにより生ゴミの腐敗率が低くなります。
完全には無くなりませんが、コンポスト内の水分調整が楽になるのは助かります。
回転型コンポスト
コンポスト本体を回転させて、生ゴミをかき混ぜられるものもあります。
定期的に生ゴミを混ぜることで、微生物が生ゴミ全体に行き渡ります。
このため堆肥に変わる時間が短縮できます。
混ぜ込む手間もかなり省けるため、手間も減ります。
屋外型コンポストの欠点
メリットが増えた屋外型のコンポストですが、いくつか不便になった部分もあります。
・スペースが必要
・堆肥の回収
容器が大きくなったが故に、細かい機能が省かれてます。
液肥が回収できない
液肥を回収するための取り出し口が無いコンポストが多いです。
地面に被せるタイプではそのまま液肥も染み込んでしまい回収不能。
回転式では、堆肥が回転することで取り出し口に詰まりやすいのか、これも無し。
液肥は水分に大量の栄養が溶け込んだ有用な肥料です。
液肥回収も重視しているなら、少々不向きたコンポストです。
畑の隅にでも設置して、後で液肥が染み込んだ土を回収しましょう。
設置スペース
コンポストの四方が60cm以上あるものが多いです。
高さも1m以上あります。
地面に被せるタイプでは、それも相まって設置場所に困ることも。
できれば液肥が染み込んでも問題ない、畑近くに設置するのが好ましいです。
堆肥の回収が面倒
大量の生ゴミを処理できる反面、堆肥の回収が面倒なものがあります。
堆肥は堆積した下のほうから出来ていきます。
そのためできた堆肥を取り出すには、一度堆肥の山を崩さないといけません。
下に堆肥を取り出せる回収口があるコンポストだと、堆肥を回収しやすくなります。
順次できた堆肥を回収したいなら、回収口のあるコンポストを選びましょう。
ミミズを使ったミミズコンポスト
ミミズコンポストはミミズ、特にシマミミズを使って生ゴミを処理してもらいます。
ミミズの管理などの手間はありますが、堆肥ができるスピードや失敗する要因が少ない点が挙げられます。
ミミズコンポストの長所
やはり目を引く長所は堆肥を作りやすい・失敗しにくい部分が目立ちます。
普通のコンポストでは失敗しやすい部分をうまくカバーできていることが多いです。
・腐敗が起きにくい
・勝手に増えるミミズ
このように、堆積型のコンポストの問題点が解決されています。
ミミズを扱うのに抵抗が無ければおすすめできる方法になります。
すぐに堆肥に変わる
一番の長所は通常のコンポストに比べ、遥かに早く堆肥に変わります。
ほうれん草の茎などの柔らかい生ゴミでも、通常のコンポストなら3週間以上はかかります。
しかしミミズコンポストなら1~2週間ほど、早ければ数日で堆肥に変えてくれます。
通常のコンポストが完全に微生物のみに頼っている点に比べ、ミミズコンポストではミミズ+微生物で生ゴミを分解しています。
ミミズの体内はより微生物が繁殖・活動しやすい環境のため、食べた生ゴミの分解も早く進みます。
生ゴミが変わるスピードが気温に左右されるのは同じですが、それを加味しても早く処理できます。
すぐに堆肥に変わるため、生ゴミの最終的な処理速度もかなり上になります。
これが他の失敗要因の抑制にもなっています。
腐敗が起きても処理してくれる
生ゴミの腐敗が起きても、ミミズはむしろ腐敗した生ゴミをよく食べてくれます。
ミミズは歯が無いため、腐って柔らくなったものしか食べません。
そのためむしろ早く生ゴミを腐らせた方が堆肥が早くできるということです。
そして腐敗した生ゴミを優先してたべるので異臭もなく虫も湧きづらくなるります。
しっかりミミズが繁殖しているコンポストは、臭いなんてほとんどありません。
失敗や不快感の原因を減らすのにミミズコンポストは優れています。
ミミズは勝手に増える
ミミズコンポストに使われるシマミミズは繁殖力が強く、幼体でも1~2か月で卵を産めるほどに成長します。
そのためかなりのスピードで増えていくため、生ゴミの処理スピードも上がっていきます。
コンポスト内に数百~千匹以上のミミズがいることなんてザラです。
もし増えすぎても限界以上には増えないので、わざわざ減らす作業も必要ありません。
死骸は堆肥に
ミミズが死んでも死骸は堆肥として分解されるので問題ありません。
そのため死骸が原因の異臭といったものもありません。
増えたミミズの分だけ堆肥も増えますし、ミミズが減っても卵からミミズが産まれる、というサイクルが出来上がります。
こうしたことで無駄なく堆肥を作り続けられます。
ミミズコンポストの欠点
スムーズに堆肥を作れるミミズコンポストですが、何も欠点が無いわけじゃありません。
・ミミズの処理限界
・コンポストの種類
・ミミズの管理
ミミズ由来の欠点がかなり多いです。
特に「ミミズがちゃんと生ゴミを食べるかどうか」によって、生ゴミの処理スピードに大きく影響します。
そのためミミズが生ゴミを食べれる環境にするのが大切になってきます。
生ゴミをえり好みする
生ゴミを早く処理してくれるミミズですが、固い生ゴミはなかなか食べてくれません。
そのため固い生ゴミだらけだと、短期間で堆肥に変わりません。
「人参やジャガイモの皮ばかり残ってた」みたいなのもザラにあります。
固い生ゴミはある程度腐敗して柔らかくならないと処理できません
そのため通常のコンポストとあまり変わらない状態になります。
ただ生ゴミが残っていても「腐っていないから食べていない」ため、臭いはほとんどしないのは良い点です。
処理量に限界がある
ミミズが処理できる量以上を投入しても生ゴミが溜まり続ける一方になります。
ミミズがベストコンディションなら、1日に食べる生ゴミは自分の体重の半分。
それより生ゴミの量が多いと処理しきれません。
あまりにも生ゴミが溜まりすぎると、一部が腐敗して虫が沸く可能性も出てきます。
…まあ、それでも腐敗した部分から食べてくれますが。
大量の生ゴミが出るなら、最低でも生ゴミの倍の量(重さ)のミミズを確保する必要があります。
ただ、ミミズは場所が狭いと増えずに数を調整するため、広いコンポストが必要です。
ミミズの量が少なすぎるとこうしたことが起きるため、初めから大量のミミズを用意すると対処しやすくなります。
ただ処理しきれないとっても、生ゴミが溜まっていってもそれは普通のコンポストと同じ状態になるだけです。
そのため堆肥ができる = 処理したと見るならば、ミミズコンポストのほうが優れているといえます。
専用のコンポストが少ない
かなりニッチなジャンルなためか、ミミズ専用のコンポスト容器が殆どありません。
国内・外含めて数種類しかないと思われます。
国内メーカーは1社しかないかと…。
おまけに値段も通常のコンポスト容器に比べると高いです。
そのためミミズコンポストをするには、
・通常コンポストで代用する
・自作する
この3択から選ぶことになります。
他のコンポスト容器でもできなくは無いですが、ミミズの分別作業がかなり大変になります。
機能に確実性を持たせたいなら、ミミズ専用コンポストを使ったほうが無難でしょう。
ミミズの管理
まずミミズが逃げ出す可能性があります。
「どうやって容器からミミズが逃げ出すの?」と思うでしょうが、ミミズは垂直な壁でも張り付いて登ることができます。
そのためコンポスト内の環境が悪くなると、壁をよじ登って逃げ出すことが多いです。
餌(生ゴミ)が少ない・水でビチャビチャといった状態になると、その傾向も高くなります。
そのためミミズが逃げ出さないよう、ある程度配慮する必要があります。
あと堆肥を取り出した後、堆肥からミミズを分離・取り出す作業が必要になります。
ミミズ専用コンポストでもなければ手作業で堆肥と分離させるしかありません。
短くても1~2時間くらいかかるのはザラです。
状況に合わせた使い分けを
コンポストの長所・短所を比較したらこんな感じの結果になりました。
私の場合ミミズが早く処理してくれそうな生ゴミはミミズコンポストへ。
それ以外の生ゴミは通常のコンポストにまとめて放り込んでます。
特にこだわりがないのなら、両方やってみるのも手かと。
それぞれ一長一短あるので、皆さんの好きな方法で生ゴミ堆肥を作りましょう。