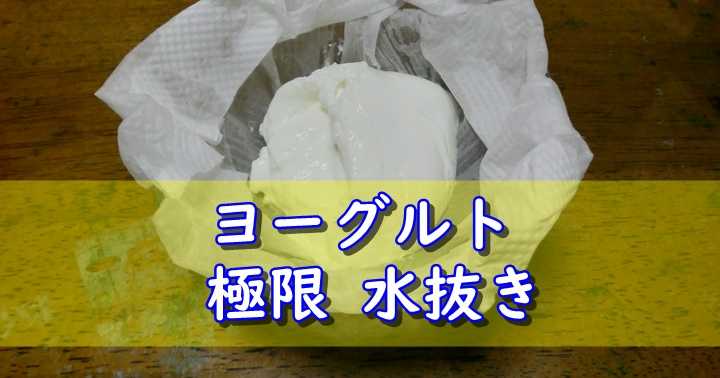大便の成分やできるまでの過程・腸との関係。便になるまでの長い旅路
大便は、できるまでに色々な過程を経ています。
大便を形作っているものや成分、消化されたものがどうなるのか等。
こういったことを理解すれば便秘の原因の一端もわかってきます。
今回はどのような仕組みで便ができるのか解説していきたいと思います。
理解すれば便秘の改善にも一役買えるでしょう。
便とは?
便のことを「食べたものの絞りカス」的なものだと思っている人が多いでしょうが、実際はかなり違います。
便を構成する成分としては
・いらなくなった腸内細胞
・腸内細菌
・体内分泌液
・消化できなかったもの
・毒素全般
このようなもので構成されており、食べたものの残りといった意味では全体の数%ほどしかありません。
「消化できなかったもの」は食物繊維がメイン。
よほど胃などの調子が悪くなければ、食べたものはキチンと消化されて体内に吸収されています。
ではそれぞれどういったものなのか個別で紹介していきます。
水分
便の中で最も多いのが水分で、正常な便なら60~70%ほどが水分でできています。
これより少ないと固めの便になっていき、逆に多いと水っぽい便になります。
水分が少ない固い便だと便秘になりやすく、水分が多い便だと下痢の原因になります。
摂取した水分の大半は体内に吸収されますが、自然と便に残る水分も多いです。
この水分が便を「膨らまして」いる状態になります。
仮に完全に乾燥した便の見た目は、全体の3割ほどとなります。
この3割ほどの成分が以下の成分になります。
腸内細胞
便の成分で次に多いのが腸内細胞になります。
この腸内細胞は役目を終えて腸から剥がれ落ちた細胞のこと。
便の「見た目」の成分としては20%ほどと最も多いです。
腸内細胞は腸内の皮膚みたいなもので、剥がれ落ちた腸内細胞はいってしまえば腸の垢みたいなものです。
腸内は消化してできた成分を効率よく吸収するため、グネグネした構造で表面積を増やしています。
そのため意外にも剥がれ落ちる細胞も多くなっています。
「そんなに多いのか?」と疑問に思うでしょうが、腸の表面積はかなり広いです。
小腸・大腸の表面積を合わせると、約300平方メートルはあるそうです。
広さはテニスコート1.5個分と同じくらい、長さなら15メートル四方という、かなりの面積を誇ります。
面積は小腸が200平方メートル、大腸は約100平方メートルほどと、小腸のほうが広いです。
小腸は栄養をメインで吸収するため、かなり入り組んだ構造をしているから。
大腸は水分を吸収するので、それなりに入り組んでいますが、そこまで複雑な構造ではありません。
これほどの広さを持つので、腸内細胞だけでもかなりの量になると想像できると思います。
水分が全体の60%として、残りの40%の半分以上。
仮に便がカラカラに干からびた状態になった状態だと、この腸内細胞をメインとして便が残ることになります。
腸内細菌
腸内細菌とは腸内に生息する菌類のすべてを指します。
「悪玉菌」といわれる大腸菌や、「善玉菌」といわれる乳酸菌なども含みます。
死んだりして活動を停止した腸内細菌の死骸も便には多量に含まれています。
もちろん「生きた」腸内細菌も。
腸内細菌は腸内に入ってきた食べ物を食べて繁殖するため、食事の量が増えれば自然と増殖していきます。
「食べた分だけ便の量も増える」のは事実ですが、それは食べたものそのものではなく「食べたもので成長・増えた腸内細菌」も便の体積の一助になっています。
割合としては腸内細菌に次いで1割ほどを占めており、便を構成する主成分といえます。
体内分泌液
この体内分泌液というのは「胆汁」などを代表とした、腸内に分泌される体液のことを指します。
例えば胆汁は食べ物に含まれる脂肪分の吸収を良くするために、肝臓から十二指腸に分必されます。
腸内で栄養の吸収をよくする分泌液ですが、余った分はそのまま便に混じって排出されています。
ちなみに便が茶色なのはこの胆汁が混じっているからです。
消化できなかったもの
「消化できなかったもの」というと消化不良を起こしていると思われます。
が、食物繊維といった食べたものの一部はそもそも消化できなかったりします。
量としてはかなり少ないですが、これも便を構成する一成分になります。
食物繊維を多く摂ると便がかさ増しされるので、より排出を促しやすくなります。
腸内細胞や腸内細菌の死骸が付着する軸にもなるので、より便がひと塊になりやすくもなります。
大きい雪玉の最初の小さな玉のごとく。
ただし胃の調子が悪かったり、よく噛まずに食べ物を飲み込むと「消化しきれなかったもの」になります。
そうすると消化しきれず、そのまま便として排出されるようになります。
健全な便は食べたものの残りはほとんど含まれていないです。
食べたものがそのまま出てきたような大量の便が出た場合、消化不良を起こしている可能性があるので注意しましょう。
毒素全般
アンモニアなど身体に害のある成分も便と共に排出されます。
ただこういった成分はそこまで重くないので、便に含まれる量(重さ)としては「一応ある」程度になります。
しかし便は体内の毒素を排出する「デトックス効果」を最も持っているものです。
逆にいえば便が出ないと体内の毒素が残り続ける・濃縮されることになります。
便がある大腸は主に水分を吸収する役割を持ちますが、便から漏れ出た毒素が水分に混じれば体内に入り込んでしまいます。
便秘が体調不良につながるのはこうした理由です。
食べたものが便になるまで
では食べたものがどのようにして便になっていくのか?
食べものが身体に「入って」から「出る」までの流れを紹介します。
口
まず「食べる」といったら口で噛むことをイメージすると思いますが、ここから食べたものの「消化」のプロセスは始まっています。
まず「よく噛む」ことで食べ物を細かくし、唾液をよく混ぜこんでいきます。
食べたものが細かくなればなるほど、消化するために必要な時間が短縮されます。
そして唾液には炭水化物と脂肪分を分解する働きがあり、よく絡めることで消化する時間を短縮できます。
…というよりも炭水化物と脂肪分は胃(胃酸)では消化できないので、ここである程度消化する必要があります。
これを逃すと、炭水化物と脂肪分が消化されるのか胃を通り過ぎたあとになります。
胃
糖質や脂質を分解するのは唾液の仕事ですが、タンパク質を分解するのが胃の役割になります。
胃で消化するといえば「胃液」ですが、胃液は「胃の中で出る塩酸」のことで、ph1~1.5と高い酸性を示します。
理科の実験でやったことがある人はわかるでしょうが、塩酸は大半の金属も溶かしてしまうほどの酸性を持ちます。
中性の水がph7前後で、0に近づくほど酸性度は上がるのでどれほど高いかわかると思います。
小腸
食べたものの栄養を吸収するのは小腸の役割ですが、その小腸にもいくつか種類があり、役割も違います。
小腸は6m以上の長さがあり、その中で別々の役割を持ちます。
・空腸
・回腸
上から順に大腸へと通じています。
十二指腸
胃で消化されたものは次に十二指腸に運ばれます。
ちなみに胃液がまだ食べ物に混ざったままなので、まだ消化作業は継続中です。
先ほど書いたように「胆汁」もここで排出され、消化した脂肪分の吸収を助けます。
消化+吸収をしている器官になります。
ちなみに十二指腸の長さは約25cmほど。
意外と短いです。
空腸と回腸
知らない人もいるでしょうが小腸と大腸の間にはまだ腸があります。
それが「空腸」と「回腸」になります。
両者の明確な境目は判別しづらく、合計して6m近い長さがあります。
「大腸が一番長い」と思っている人も多いでしょうが、実際はこの空腸と回腸が一番長いことになります。
ここでも胆汁のように「腸液」という、タンパク質を吸収しやすいアミノ酸に分解する液が出ます。
糖質・脂肪分・タンパク質(アミノ酸)などの栄養や、空気といった気体もここで吸収されます。
大腸
「腸」といわれて頭に浮かぶのがこの大腸でしょう。
大腸の役割は主に水分の吸収になります。
小腸では食べ物に含まれる水分の吸収はされず、例え水だけを飲んだとしても大腸までそのまま流れていきます。
また食べたものが明確に「便」といわれるようになるのも、この大腸に流れてきてからになります。
長さは約1.5mほどと小腸よりかなり短いですが、「便」になってからはかなり長い時間滞在します。
大腸は便を留めておく大事な部位でもありますが、その間も常に水分の吸収は続いています。
ここで水分を吸収されすぎると便が固くなり、便秘の原因にもなります。
逆に水分が吸収されないと下痢の原因に。
できれば便意が出たら我慢せずにトイレで出すようにしましょう。
今日出した便は「2日前」に食べたもの
食べたものが胃で消化されるのは、食べ物の種類にもよりますが最長でも肉類で6~8時間ほど。
しかし消化された残りが便として排出されるのは2日経ってから、早くても1日経ってからです。
小腸~大腸の長さは合計して8m前後になりますが、最短でも24時間はこの中を移動していることになります。
逆に言えば、栄養の吸収にはそれほどの時間が必要ということ。
食事して少しした後に便意が出るのは、「新しい便ができるから、古い便は押し出せ」といった具合の仕組みです。
つまり食後は便を出す絶好の機会ともいえます。
よく消化できていれば便になるのも早く、「ムダの無い便」ができやすくなります。
食べ物を効率よく消化する方法は別に記事にしてあるので、興味がある人はどうぞ。
便の意外な部分
食べたものが便として出てくるには、このような工程を得てからになります。
調べていて驚いたのが
・「小」腸のほうが「大」腸より長い
この2点ですかね。
案外食べカスが便の元になってるのかと思いきや。
そのほとんどは消化されていて、大部分は関係ないものでできていたのが初めてわかりました。
「食べた物を消化・吸収する」という点では、身体はしっかりやってるんですよね。