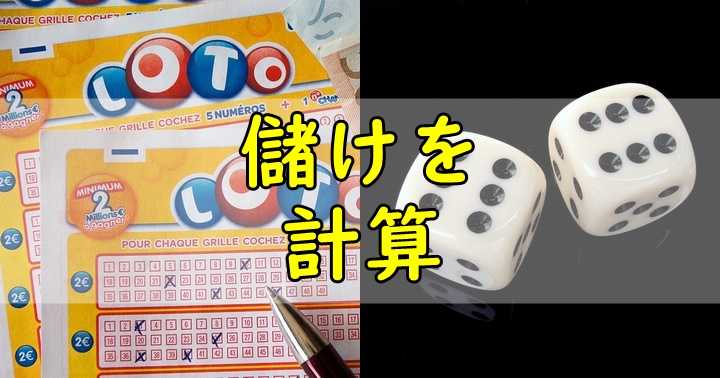雷についての豆知識。ファンタジーではカッコイイ、日常では災害になる現象の正体
一般的な日常生活では災害。
ゲームやアニメでは「なんかカッコイイ、強い」といったイメージのある雷。
そんな雷ですが、どういった原理や現象を伴って発生しているのか?
若干廚二病な感じがしますが、どうぞ。
「雷」の名前の由来
いなづま」「いかずち」と、同じような現象を指すのに別の名称が使われることがあります。
いくつかメジャーな呼び名を調べてみたらこうなりました。
雷(かみなり)
一般的な呼び名ですが、気象上の定義としては「10分以内に雷鳴か雷電が発生した場合」を雷といいます。
雷鳴は雷の音のこと。
ただ、雷電は雷と同一視されるものの、微妙に違ったりします。
雷電(雷電)
雷電は雷の音と光が起きる放電現象のことを指します。
一般的に認識されている雷は大抵この雷電のことになります。
雷(いかづち)
雷(かみなり)と同じ漢字で雷(いかづち)と読むこともあります。
づ…助詞の「つ」
ち…「大蛇(おろち)」や「水霊(みづち)」の意
雷が落ちるときに蛇のような激しい動きをすることから、こんな感じで古来の日本語を語源として読まれます。
稲妻(いなづま)
雷を日本風にいう「稲妻」。
結構昔から使われている呼び方だそうです。
季節上雷が起きやすい時期と稲の開花時期が重なることが多いです。
そのため「稲穂が雷のおかげで開花する」と信じられていたそうです。
夫婦のように一緒にある存在として「妻」がつけられ「稲妻」と呼ばれるようになったとか。
「いなずま」と書かれることもありますが、語源の由来から考えると「いな”づ”ま」のほうが正しそうです。
雷の正体
雷の大本は雲の中で蓄積された静電気です。
もっと詳しくいうと、雲を構成する水分子同士の摩擦で発生しています。
「細かい分子とはいえ、水で静電気が発生するの?」と思う人もいるでしょう。
静電気はあらゆる物質同士の摩擦で起きます。
ご存じのとおりプラスチックなどの石油製品は電気を通しません。
これを「絶縁体」といいます。
そのため電気コードはビニールといった絶縁体で覆われており、電化製品でも多用されています。
しかし電気を通さないものでも、物質の表面上で静電気を発生させることはできます。
例えば下敷きを脇などで高速でこすって髪の毛に近づけると、髪の毛が下敷きに引き付けられます。
このように絶縁体でも電気を発生させることは可能です。
静電気は摩擦さえあればなんにでも発生します。
そのため水分同士の摩擦でも静電気が起き、それが雷の「電源」のようなものになっています。
雷の威力・スペック

いよいよ廚二病くさくなってきましたが、雷のスペックを紹介します。
元となる静電気のスペック
「雷が人に落ちるとまず助からない」というのが常識です。
が、そもそも静電気が元なのになぜそこまでの威力になるのか?
静電気は電気の力を表す「電圧」はかなり高いです。
家庭用コンセントが100ボルトに対し、静電気は数千ボルトといった数値になるのが普通です。
ではそれだけの力を持ちながらも、なぜ「痛っ!」程度で済むのか?
それは静電気は電気の量を表す「電流」が非常に少ないからです。
水でイメージするとわかりやすくなります。
例えば水滴1滴を頭上に落とされても、特になんともありません。
これが同じスピード(力)だとしても、1L・10L・あるいは1000L(1トン)と量が増えていくとどうなるか?
…簡単なイメージでもヒドイ状況になることは予想できると思います。
これと同じで、電気でも人体に深刻な影響を与えるのは電流(量)が重要な点になってきます。
雷のスペック
では雷の基本的なスペックですが、以下の通り。
速度:秒速200km前後
雷の速度はおおむね秒速200kmほどと計測されています。
「時」速ではなく「秒」速なので間違えないよう。
時速に直すと72万km/hとなり、かなりの速度だと感じやすくなると思います。
ちなみに自然界最速といわれる光速は秒速30万kmです。(時速10億8千万km)
…桁が違いすぎて遅いと感じるかもしれませんが、実際に雷はトップクラスの速度を誇ります。
音速は時速1225kmで、雷のおよそ1/600とかなり遅いです。
落雷の際に音が遅れてくるのはこのため。
ワット数:900ギガワット
電気的エネルギーの表現方法であるワットですが雷のワット数は実に900ギガワット。
1ギガワット = 1,000,000キロワット(100万キロワット)。
なので、900ギガワット=900,000,000キロワット(9億キロワット)とケタ違いのワット数を誇ります。
一例として、近年の発電所の1日の電力の供給量が7500万キロワット前後。
ピンキリですが1本の雷で発電所10個分の発電量と大差ないワット数になります。
ちなみに日本の1日の総消費電力量は大体70000ギガワットとのこと。
計算上はおよそ80本の雷で日本全土の電力をまかなうことが可能です。
雷は大抵一度に数回は発生するので、雷ができやすい雲だと日本全土で相当数の雷が発生してそうです。
仮に雷をそのまま電力に変換できたら電力の消費問題もかなり解消されます。
早く実現しないですかね?
電流:数十万アンペア
雷は大本となった静電気と比べ、ケタ違いに電流の量が高いです。
家庭用コンセントではたった15アンペア。
対して、雷の場合数万~数十万アンペアまで跳ね上がります。
コンセントの電流を水道の蛇口から出る水量とすると、雷ならダムが決壊したレベルの水量になります。
これが雷で人が死にかねない理由です。
電圧:数億ボルト
電気の力を示すことでおなじみの電圧(ボルト)。
雷は数億ボルトと電流と同じくとんでもない値になります。
某電気ネズミの技の「10万ボルト」と「かみなり」、どっちが強いとなると当然「かみなり」になります。
それこそ雲泥の差で。
家庭用コンセントの電圧はご存じ100ボルト。
雷と比べればデコピンとトラックとの正面衝突くらいの差があります。
温度:3万℃
電流同様になかなか焦点が当たらない温度ですが、雷の周囲の温度は3万℃。
日常ではまず経験しないほどの高温になります。
雷が落ちたときに鳴る雷鳴はこの数万にもなる温度が原因です。
空気というのは温度が上がるほど膨張していきます。
そして瞬間的に空気が高温になると、それこそ急に空気を入れた風船のごとく破裂したような音を出します。
これが「雷鳴」となって聞こえてきます。
ちなみに鉄が溶ける温度はこの温度に比べるとわずか1538℃ほど。
鉄すらも一瞬で溶かしてしまいそうな雷の温度です。
ではなぜ落雷にあった木などが一瞬で灰になったりしないの?
それは雷が内部を通るのが刹那の一瞬だからです。
火の上を手でサッとするようなもの。
落雷にあった木が即座に燃え上がらないのが多いのはこのためです。
ただ不幸にも落雷が落ちた人がネックレスなどの貴金属を身に着けていた場合、溶けて変形してしまうことが多いそうです。
雷からの避難方法
雷が鳴ったらまずどこに避難すべきか?
一番いいのは「高いものから少し離れた場所」だそうです。
雷は高い場所に落ちやすいというのは常識です。
しかしより落ちやすいのは金属の鉄塔・次点で高い樹木といったところです。
そのためできる限りそういったものから4mくらい離れた場所がいいそうです。
「真下のほうがいいんじゃ?」と思う人もいるでしょう。
しかしこれはかえって危険です。
例えば樹木の下に避難したとします。
そして例え最初にその樹木に雷が落ちたとしても途中で人のほうに雷が通電する危険性があります。
これは樹木より人のほうが電気を通しやすいため。
最初は樹木の中を進んでいた雷が、より通電しやすい人に誘電されるそうです。
こういったことから、雷から避難する場合は高いものからつかず離れずの場所にいるのが最適だといわれています。
その上で姿勢を低くして雷が過ぎ去るのを待ちましょう。
逆に10m以上と距離が離れすぎると、かえって雷が落ちる危険性があるので注意しましょう。
車の中にいると感電しにくい
運転中に自分の車に雷が落ちたらどうなるのか?
金属の塊の中ですからヒドい事になりそうですが、意外と気が付かないものだそうです。
感電して失神したとかいうわけではなく。
先ほど「樹木より人のほうが通電しやすい」と書きました。
しかし車の中では逆に車の金属フレーム部分を優先して通っていくので、人が感電することは少ないそうです。
ただ指輪やネックレスといった貴金属を身に着けている場合は別。
それを起点として感電する恐れがあります。
運転中に雷が鳴り始めたら、身に着けた金属は取り外したほうが無難です。
火山活動でも雷は発生する
雷は空(雲)で発生すると思っている人が大多数だと思いますが、火山活動でも雷は発生します。
これを「火山雷」といいます。
火山の活動が活発になると真っ黒な噴煙を出し始めますが、この噴煙の中でも雷は発生します。
噴煙では火山内部の灰などの細かい物質が大量に巻き上げられます。
その物質同士の摩擦で静電気が発生します。
これで雲の中で静電気が発生するのと同じような状況になり、同様に雷が発生する仕組みになってます。
動画で見てみると、普通の雷とはかなり違いがあります。
延々と上り続ける噴煙も相まってホントウに「災害」と感じることができるものです。
常に雷が落ち続ける場所がある
どこぞのファンタジーのような、1年中ずっと雷が落ち続けているという恐ろしい場所があるのをご存じですか?
ベネズエラにあるマラカイボ湖、その湖に繋がるカタトゥンボ川という川の河口付近がその雷スポットらしいです。
ここで起きる雷の通称は「カタトゥンボの雷」。
「1時間に3600本の雷が走る」ということで公式にギネス記録にも載るほど有名です。
普通の雷は1本・または数本の雷が空に走るだけです。
が、ここでは数十本以上の雷がかたまりとなって空を走ります。
本当に映画やゲームでしか見ないような光景です。
ちなみにここでは音が鳴らない雷が度々発生するそう。
「光のみが発生する」ということで「マラカイボの灯台」と、大航海時代から船乗りたちの指針となっていたそうです。
最後に
雷に関する豆知識を簡単に紹介しましたがいかがだったでしょうか?
科学的な視点から廚二病的なものまで。
総じていうと災害と認定できるだけのスペックは持っているということです。
よくテレビなどで「雷から無事に生還した人!」なんて見たりしますが、はっきりいってレアケース。
大半の人は良くて後遺症が残るレベル、悪ければ即死といったものばかりです。
皆さんも「雷は災害」という認識をきちんと持って対応するようにしましょう。