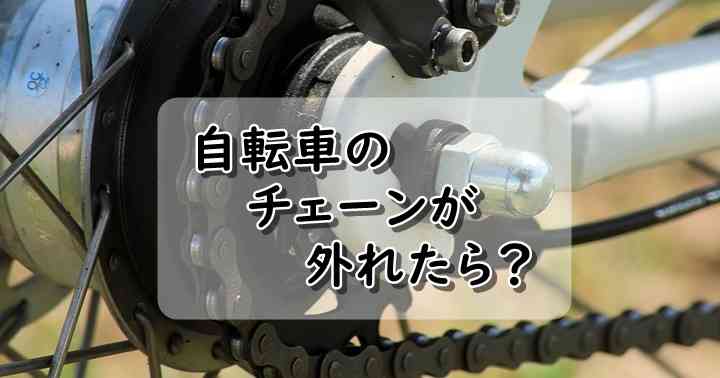速度が出る・利便性がある自転車とは? 市販されてる自転車の種類
自転車にはいくつも種類があり、それぞれで出せる速度などに違いが出ます。
速度重視、利便性が高い、オールラウンドなど。
設計からして自転車の性能は大きく違います。
今回はそんな自転車の大まかな種類を特性などを含めて紹介したいと思います。
速度が出る・出ない自転車の違い
まず速度が出やすい自転車の特徴を解説します。
・カゴなどのパーツが少ない
こうした設計の自転車は、速度が出やすい設計になっています。
まずペダルを漕ぐ間に前傾姿勢になりやすい自転車では、風の抵抗が少なくなります。
ロードバイクやクロスバイク・マウンテンバイクでは、人力でも速度が出しやすいイメージがあると思います。
仕組みとしては、前傾姿勢になれば身体に当たる風を受け流せるからです。
自転車を漕いでいて風の抵抗を減らそうと思うと、自然と前傾姿勢になると思います。
競輪選手をイメージすればわかりやすいですが、これでもかってくらい頭を下げて風の抵抗を無くしています。
特に頭~腰の高さが同じくらいになる前傾姿勢では、かなり風の抵抗が少なくなります。
逆にシティサイクルでは立った状態で漕ぐため、上半身部分に風が当たって抵抗が大きくなります。
ママチャリでは速度が出にくい一因はこれもあります。
また、カゴなどのパーツを外して重量を減らし、速度を出やすくすることもできます。
単純に自転車そのものの重量を減らせば、その分漕ぐ力を少なくできます。
重量を減らす以外にも、パーツに当たる風の抵抗を減らす目的もあります。
こうしたことからロードバイクなどは速度が出しやすい自転車となっています。
自転車の種類は大きく分けて6種類!
世の中に出回っている自転車は、大雑把に分けると6種類に大別されます。
・ロードバイク
・クロスバイク
・マウンテンバイク
・折りたたみ式自転車
・電動アシスト自転車
おそらく皆さんが最初に使ったのは、通称ママチャリと呼ばれる「シティサイクル」になると思います。
しかし速度重視になると「ロードバイク」「クロスバイク」の方が優れています。
砂利道では「マウンテンバイク」、収納場所に困るなら「折り畳み自転車」と、用途別にかなり選べます。
では各自転車別に特徴を紹介していきます。
シティサイクル(一般車)
皆さんが最初に通学などで使うことになるのが「シティサイクル」と分類される自転車になると思います。
カゴや後部座席など必要なものが付いているため使い勝手がよく値段も安め。
主婦などを含めて買い物によく使われるため「ママチャリ」なんて呼ばれたりもします。
カゴに荷物を入れることを前提なので、運べる重量も10kg以上になっている場合がほとんどで
カゴ・後部座席・車輪の泥はね防止カバー・スタンドなどの必要と思われる機能がほぼついています。
どんな人でも日常生活の中で使いやすいように設計されています。
チャイルドシートなども後付けできるため、必要に応じて機能を追加したりしやすいです。
しかし、シティサイクルは自転車の中でもとにかく速度が出にくい種類になります。
カゴなどのパーツを多くつけているため自転車そのものの重さが増え、その分漕ぐときに力が必要になります。
自転車そのものの重量も重くなりやすく、最低でも15kgはあります。
これは自転車フレームを安価な鉄系の素材にしたり、装着されているパーツが原因。
また座る体勢の関係上風の抵抗をモロに受けるため、向かい風だと一層速度が出せなくなります。
その分追い風だと速度は出やすいですが。
機能性を重視してオールラウンドに使える分、速度といったものは落ちやすくなるのが特徴です。
おそらく速度が出なくて不満な人はこのタイプの自転車を使っていることが多いと思います。
ロードバイク
人力で最も速度を出せる自転車がロードバイクになります。
国道や河川などの直線道路で、競輪選手のようにものすごいスピードで自転車で走っている人を見たこともあるかと。
漕ぐだけでも相当な速度が出せるのがロードバイクの最大の特徴です。
とにかく速度が出せる設計で、自転車のフレームも軽く・丈夫なものが使われています。
「カーボン」や「アルミ」といった重量を軽くできる素材や、少々重くなりますが「スチール」や「チタン」といった振動を吸収しやすい素材など、使われている素材は多岐に渡ります。
サドルが高く自然と前傾姿勢になり、その結果風の抵抗を少なくできるので速度も出しやすくなります。
「風を切って走りたい!」「もっと速度が欲しい!」なんて感じる人はこのロードバイクか、後述する「クロスバイク」がオススメです。
しかしシティサイクルとは逆に、ロードバイクで目立つデメリットがカゴや後部座席などの機能が無いことです。
一般的なシティサイクルでは装着されているパーツは軒並み排除されてしまっています。
・後部座席
・泥はね防止カバー
・スタンド
これらのパーツがなく、日常で使うには不便なところがあります。
これは車体の重量を軽くして速度を出しやすくしているため。
そのため単純に走るため・荷物を持たずに移動するためくらいにしか使えません。
またハンドルの形状の関係上、別売りの大きなカゴなどをつけるのは難しいです。
手荷物はリュックなどで背負うしかありません。
こうした風にシティサイクルでは標準でついていた機能の追加がしにくいです。
速度が出過ぎるため、住宅密集地などの小道や道路の幅が狭いところではかえって危ないです。
道路の幅が広く直線的な国道などの道路を走るのに向いています。
クロスバイク
クロスバイクは利便性とスピードの両立を目指したタイプの自転車。
シティサイクルとロードバイクの中間的な自転車になります。
ただスピードを出しやすいようフレームなどの設計・構造はロードバイク寄りになっています。
ロードバイクほど速度は出ないものの、その分小回りが利くため入り組んだ道でも走りやすいです。
ロードバイクでは外されているカゴやスタンドなども付いていたりするので、日常生活でも使いやすくなっています。
「通学・通勤で使いたい」「速度が出て、買い物でも使える自転車がいい」なんて思っている人に最適な自転車です。
速度を出しつつ、利便性も欲しい人ならクロスバイクを使ってみましょう。
欠点としては、シティサイクルとロードバイクの中間的な機能性のためか、少し中途半端なところがあります。
商品によってはパーツがあったりなかったりと、機能性がマチマチなことも多いです。
このため欲しい機能は別売りのパーツを取りつける必要性が出てきます。
ただ別売りのカゴだと耐荷重量が5kgくらいしかないものも多く、手荷物は少な目にする必要が出てきたりします。
逆に手荷物が少ないならシティサイクルより速度を出しながら走れるので、自分が使う場面を想定してから商品を選びましょう。
マウンテンバイク
マウンテンバイクは山道などでの走行に適した自転車です。
山道などのオフロードでは急斜面・走行中の衝撃などとにかく自転車に負担がかかります。
そのためロードバイクのような軽量かつ丈夫な素材でフレームが設計されており、タイヤも山道専用に頑丈なものが使われています。
舗装されていない砂利道でも走行できるので、人によっては平地でも使う機会はあると思います。
悪路を走行すること前提なので泥はね防止カバーも標準でついており、追加でつける手間も省けます。
カゴなども付いていたり後付けもできるので、もし山道などを荷物を持ったまま走るならマウンテンバイクを使う事も視野に入れましょう。
デメリットとしては、ロードバイクと同じく専門性が高いタイプの自転車なので、使える場面は限られます。
オフロードでの走行に適した設計にはされていますが、普通の舗装された道路ではあまり意味がありません。
オフロードでもパンクしにくいようタイヤがぶ厚く頑丈になっている反面、普通のタイヤより重量も重くなっています。
趣味、あるいはやむを得ない場面以外では日常生活で使う機会には恵まれないかと。
クロスバイクやロードバイクをオフロード仕様にしただけともいえるので、普通の道路を走行するならそちらの種類を選びましょう。
折りたたみ式自転車
折りたたみ自転車はその名の通り、折りたためて収納できるので持ち運びが容易です。
自転車も小さめのものが多く、半分に折りたたむ形になるので、車などにも簡単に積め込めます。
折りたためれば玄関や物置にも簡単に入るサイズになるので、自転車の置き場所が無い人にはオススメです。
シティサイクルをそのまま折りたたみ式にしたものもあるため、カゴといった基本機能がついているタイプもあります。
もしカゴなどが付いていなくても別売りのカゴなどを後付けできるため、利便性を上げることもできます。
ただし折りたたみ式自転車では、シティサイクル同様あまりスピードを出しやすい設計ではありません。
小型化した影響でタイヤも小さく、漕ぐ力がタイヤに伝わりづらいです。
あくまでも「収納性」を高めた自転車なので、走行速度や利便性などは二の次になっている場合が多いです。
特に背の高い人だとかなり漕ぐのが大変になるので、購入する前に一度試乗してみて使い心地を確かめましょう。
電動アシスト自転車
電動式でペダルを回してくれる・回すのを補佐してくれるのが電動アシスト自転車になります。
基本的にシティサイクル(ママチャリ)を電動式にしたものが多く、カゴといった基本機能を常備しているので利便性を維持したままスピードを出せるようになります。
そのため荷物が多くてもあまり負担を感じずに、普段通りに走行し続けられます。
製品ごとに違いは出ますが、大体30km以上はバッテリーが持つようになっています。
平均速度は時速15~18kmとシティサイクルより少し速い程度ですが、疲れずに長距離を走り続けられるのは大きなメリット。
年を取ったりして体力が落ちてきた人でも、平均時速10~15km(若い人並の時速)といった速度を出せすことも可能です。
自転車で通勤や買い物などをしている人にはオススメ。
収納性重視の折り畳み式や、スピードを出しやすいクロスバイク型の電動アシスト自転車もあります。
ただ電動アシスト自転車には他の自転車と違って注意点がいくつかあります。
少々重要なものなので、小分けで説明します。
こまめな充電が必要
「電動」のため、機能を十全に活かすには走る前にバッテリーをしっかり充電しておかないといけません。
走る距離にもよりますが、フルに充電しても早いと3~4日くらいで切れてしまうので、その前に充電する癖をつけたほうがいいです。
もし走行中に電動アシストが無くなると、バッテリーの重さの5~10kgくらいがデッドウェイトになり、漕ぐのが非常にキツくなります。
自転車の総重量が25kgくらいに増えるので、電動アシスト無しだとカゴいっぱいの荷物を抱えて走るようなものだと思いましょう。
ちなみに普通の自転車は10~15kgくらいの重量です。
電動「アシスト」の自転車を選ぶ
電動自転車には2種類あり、誰でも乗れるのは電動「アシスト」と表記されている自転車になります。
もう一方の「フル」電動となっている自転車では原付免許が必要になります。
原付とは「原動機付き自転車」の略で、バッテリーやエンジンなどのおかげで漕がなくても自走できるものを指します。
フル電動の自転車だとペダルを漕がなくても走行できるので、スクーターと同じ「原動機付き自転車」になります。
「アシスト」と書かれた自転車でも、たまに「フル」の機能も兼用している製品があるため注意が必要です。
流石にフルの方を購入する際には免許の有無を聞かれると思いますが、くれぐれも間違えて購入しないよう気をつけてください。
自転車の種類を選ぶ基準
機能性+スピードなら「クロスバイク」か「電動自転車」
荷物などを積んだ上でスピードを出せる自転車なら「クロスバイク」か「電動自転車」になります。
クロスバイクは、人力ながらもスピードを出せるような構造になっています。
それに加え、カゴなどのパーツが付いている・後付けできるので、用途に応じて機能を追加して利便性を高くしやすいです。
電動自転車なら電動アシストで漕ぐ負担を軽減してくれるのでラクにスピードを出せます。
シティサイクルを基本にしているため、カゴなどが標準でついているものも多いです。
日常生活で自転車をよく使う人なら、こういった利便性とスピードが出せる自転車を選ぶといいでしょう。
ひたすら風を切りたいなら「ロードバイク」
長い一本道をひたすら風を切りながら走りたい人なら「ロードバイク」を使いましょう。
全自転車の中でも特にスピードを出せるよう設計されており、他の自転車を漕ぐのと同程度の負荷でもスピードが出やすいです。
フレームの素材・車輪(ホイール)・タイヤなどの種類が豊富なので、自分好みカスタムしやすいです。
風を切って走る快感を得たいなら、是非ロードバイクを使ってみましょう。
置き場が無いなら「折りたたみ式自転車」
自転車の置き場に困っているなら「折りたたみ式自転車」で収納できるようにしましょう。
折りたためば長さ80cm・幅40cmくらいになり、玄関といった少ないスペースでも置けるようになります。
普通の車でも積み込めるくらいの大きさになるので、車の遠出でも運ぶことができます。
駐輪場などがないアパート住まいの人なら、折りたたみ式自転車で移動手段を増やしましょう。
自分に合った自転車選びを
自転車で走るからには、目的に関わらずスピードは必要です。
しかしスピードが出るということは、万一事故を起こしてしまうと相手・自分のケガの度合いも大きくなります。
くれぐれもスピードの出し過ぎや、わき見運転などの不注意による事故を起こさないよう気をつけましょう。