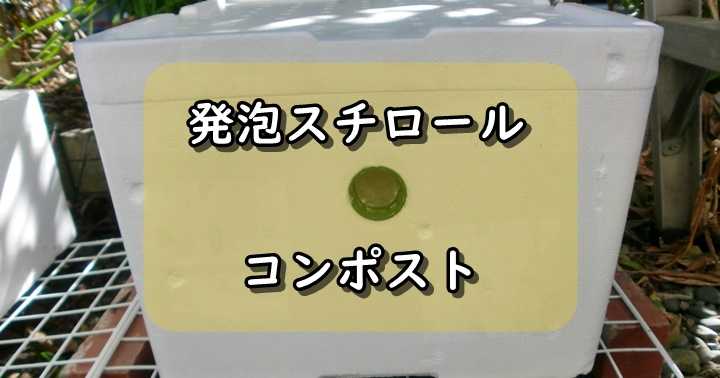野菜栽培で地味に重要な「酸性度」。 知らない内に植物が枯れる土になっているかも?
家庭菜園をしていて「しっかり肥料をやってるのに育ちが悪い」なんてことありませんか?
リン酸やチッソといった栄養などは気にする人は多いと思います。
しかし普段気にしたり調べてみたりしないのが土の「酸性度」。
この酸性度も野菜などを育てる上でかなり重要になってきます。
最悪の場合だと栄養豊富なのに植物が枯れやすい土になっていることもあります。
土の酸性度とは
土の酸性度とは理科の実験でもある「酸性」と「アルカリ性」のことです。
よく使われるのが、「酸性」では塩酸。
「アルカリ性」では漂白剤が代表的です。
酸性度はpH(ペーハー)で表され、数値の範囲は0~13になります。
pHが0に近づくほど酸性になり、13に近づくほどアルカリ性になっていきます。
中性である水のpHが7.0なので、ここを基準に「酸性」か「アルカリ性」かを判断していきます。
土でも同じように「酸性」か「アルカリ性」なのか判断でき、そのpH数値を測ることができます。
酸性度がどう影響するのか
植物ごとに適した酸性度がある
植物の生育に適したpH値は7.0以下くらいからになります。
基本アルカリ性では植物は育ちません。
ただ適したpH値は植物ごとに違いがあります。
キャベツ・ダイコン…pH5.5~6.5。
ジャガイモ・サツマイモ…pH5.5~6.0。
ブルーベリー…pH3.0~4.0。
このように植物ごとに適した酸性度は違います。
ちなみにpHの値が1違うと濃度は10倍ほどの違いがあります。
「1くらいたいして違わない」なんて考えるのは禁物です。
例え差が0.2くらいだとしても濃度は2倍くらい違うことになります。
一般に市販されている野菜の土は大体pH6.0前後なので、ほとんどの野菜は育てられます。
ただしブルーベリーのような酸性の土でしか育たない植物では、専用の土を使う必要があるので気をつけましょう。
生育障害
pHが適正濃度より高い or 低いと根のダメージになり、根が張らず枯れてしまう原因になります。
わかりやすく説明すると、酸性が高いと塩酸に触れているような感じに。
アルカリ性が高いと漂白剤に触れている感じになります。
これは極端な例えですが、危険性はなんとなくわかってもらえると思います。
pHが酸性寄りだと土中のアルミニウムが溶け出し、それも根のダメージになります。
またアルミニウムが溶けアルミニウムイオンが増えると、栄養となるリン酸を横取りしてしまいます。
日本の土壌は酸性寄りになりやすいです。
これは土壌のミネラルが、雨で溶け出して流されてしまうため。
ミネラルの代表的なカリウムやカルシウム(炭酸カルシウム)はアルカリ性です。
雨の酸性度はpH6.0前後なので、微妙に酸性寄り。
そのため土壌のミネラルと反応して溶かしてしまいます。
少量の雨なら溶けても土壌に留まりますが、雨が多いとそのまま流されてしまいます。
最近は排ガスの影響で雨そのものがpH5.0以下の酸性になっていることも多いです。
俗にいう「酸性雨」とは、濃度が高い排ガスが雨に混ざって起きる現象です。
特に排ガスが多い都心部などではその傾向が高くなります。
こうした地域ほど土壌の酸性度が酸性に偏りやすくなってます。
酸性度の測り方
土壌酸度計で測る
一番手軽なのやり方では「土壌産時計」使います。
土壌酸度計は土の酸性度を測る専用の機器です。
機器といっても15cmほどで、そんな大仰なものじゃありません。
使い方は土に刺す。これだけです。
少し湿らせた土に機器を刺せばpH値が数値で示されるので、細かく酸性度を知りたいときに便利です。
後述のリトマス試験紙と違い、何度でも使えるのでプランターなどを多く使っている人は重宝しますし、手間もかかりません。
畑の範囲が広かったり、多くのプランターで栽培している人にオススメです。
リトマス試験紙で測る
理科の実験で使うリトマス試験紙でも土の酸性度を測れます。
②混ぜた水を試験紙につける
これで土の酸性度を測ることができます。
青色の試験紙→赤色に変わると酸性。
赤色の試験紙→青色に変わるとアルカリ性です。
pH値は試験紙に同封されている比較表と色を見比べて測ることになります。
酸性度の調整の仕方
酸性度が生育に適していなかったとき、どうやって酸性度を調節するのか紹介します。
ちなみに“酸性度(pH)を上げる"とは、アルカリ性を上げるということです。(例:pH5→6)
酸性に近づけるという意味ではないので、少々ややこしいです。
酸性度を上げる(アルカリ寄りにする)
酸性度を上げるには土中のアルカリ分を増やす必要があります。
一番有効なのが「石灰」資材や、枝や草の燃えカスの「草木灰」を土にまくことです。
社会や歴史の授業で「酸性雨で枯れた森に石灰をまいた」という解説。
それと同じで石灰で酸性を中和してしまいます。
石灰系の資材もいろいろありますが、1㎡の土のpH値を1上げるには
炭酸カルシウム…200g
消石灰…160g
有機石灰…250g
このくらいの量を撒けばいいです。
ただ草木灰は灰にした材料によってアルカリ分(撒く量)が違ってきますので、使用法を読んで使って下さい。
酸性度を下げる(酸性寄りにする)
土を酸性寄りにするのに代表的なのは「ピートモス」を使うことが挙げられます。
ピートモスは水ゴケなどが堆積・発酵した植物用土で、強い酸性の土です。
代用品として似た性質を持つ、人工的につくられた土の「ココピート」というものもあります。
ただピートモスには「pH調整済み」と「pH未調整」のものがあり、
pH未調整…pH3.0~4.0
とpH値に違いがあり、酸性寄りにするなら「pH未調整」のものを使うので注意してください。
調整済みのピートモスは普通の植物用の土として使うために、敢えてpH値を中性寄りにしています。
量としてはかなり大量に使います。
例えば、60cmの細長いプランターだと、土が10リットルは入ります。
このプランターの土がpH7.0として、pH6.0に下げようと思うと5リットルの土が必要になります。
pHを1下げるだけでも、元の土の半分以上の土が必要ということに。
結構な量を使うので、20リットルといった大容量のものがオススメです。
ちなみに化学肥料の成分で「硫」「塩」とついているものは、少しながら酸性度を下げる(酸性寄りにする)効果があります。
そこまで強い効果は持ちませんが、これらを使うときは留意しておきましょう。
最後に
土の酸性度は成長をよくする肥料などと違って明確にはわかりにくいです。
そのくせ植物の生育に重要な要素のひとつでもあります。
「肥料をしっかりやっているのに育たない」なんてことが多いなら、一度しっかり酸性度を測ってみましょう。