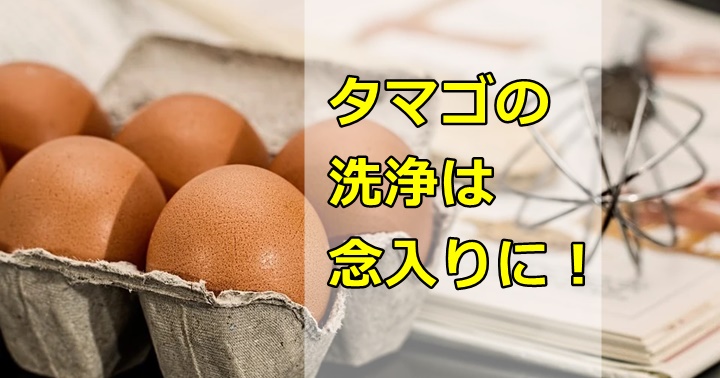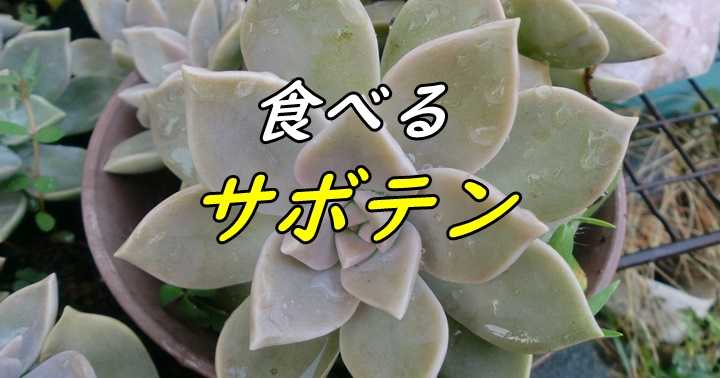野菜を育てる栄養素の種類。果実・茎・根を成長させる肥料
肥料は野菜や果物の収穫量にダイレクトに響いてきます。
しかし肥料といっても、植物の生育に必要な成分には違いが出ます。
実をつけるには?
葉を増やすには?
茎を伸ばすには?
根を生やすには?
これらには、それぞれ違った肥料が必要になります。
肥料に含まれる栄養素はいったいどんなものなのか?
その栄養が足りなくなるとどんな症状が出るのか?
そこのところを解説します。
必要な栄養は14種類!
植物、特に野菜や作物には必要になる栄養素は14種類に及びます。
厳密にいえば水素・酸素・炭素も含まれますが、これらは空気と水で補給できるので割愛します。
これらのどれかが不足してきても、順調に生育が進まなくなります。
植物の身体を構成するための「三要素」。
三要素の吸収を助ける「二次要素」。
必要量は少ないながら、生育の細かいサポートをしてくれる「微量要素」。
この3つの分類の栄養素が存在しています。
良く聞く3大栄養素
最初は最も重要な「三要素」の紹介から。
野菜を育てていると少しは聞く機会が出てくる「リン酸」「カリウム」「チッソ」です。
これらは作物そのものを育てるのに必要になります。
その分、足りないと苗や実の育ちが悪くなる影響が出やすいです。
| 役割 | |
|---|---|
| リン酸 | 実・花を大きくする |
| カリウム | 根を作る |
| チッソ | 茎や葉を作る |
このように、それぞれの栄養素が互いを補っているような状態です。
どれか一つが足りなくなっても、植物はうまく成長しません。
リン酸(P)
リン酸は「リン」と省略して呼ばれることが多く、元素記号の「P」で表記されることもあります。
リン酸は花や実をつけるのに必要で、作物を大きくしたいなら必ず必要になる栄養素です。
そのため実や苗の生育が悪いようなら、まずはリン酸を与えるところから始まります。
こうしたことから「花肥」「実肥」と呼ばれることもあります。
他の栄養素と比べ水に流されにくいので土の中に滞留しやすいです。
そのためロスが少なく、キチンと与えていればその分吸収されます。
しかし必要量も多く、足りなくなると作物が大きくなりません。
特にトウモロコシ・大玉トマト・ナス・大根といった大ぶりの野菜。
これらはリン酸が少ないと実が生りません。
リン酸が不足すると葉が濃い緑色・赤・紫色などの色に変色したり、下のほうの葉が落葉したりします。
リン酸は有機肥料ならどれもそれなりに含んでいますが、特に多いのは「骨粉」です。
化学肥料なら「熔リン」あるいは「過リン酸石灰」と書かれた単肥(単一成分の肥料)が特に多いです。
カリウム(K)
カリウムも「カリ」と省略されて呼ばれる場合があります。
元素記号の表記は「K」です。
カリウムの重要な役割は植物の根を作ることで、通称「根肥」ともいわれるほど。
根を広く・深く張ることができればたくさんの栄養を吸収できます。
リン酸と同じく植物の生育に欠かせない栄養素です。
逆にカリウムが足りないと根の張りや生育が悪くなります。
根が育たないと水分や栄養を吸収できず、植物の生育全体に影響してきます。
それに根がうまく張れていないと、少しの風や、植物そのものの重さで倒れてしまうことがあります。
他にも生育後期に葉の先や端の部分が黄色くなり、枯れやすくなります。
草木灰などには比較的多く含まれていますが、与えすぎることで土の「アルカリ化」に注意。
単肥なら「硫酸カリ」「塩化カリ」と書かれた肥料が当たります。
チッソ(N)
チッソは植物の茎や葉をつくるのに必要になります。
元素記号は「N」。
さしずめ植物の「身体」を作っているようなものです。
「葉肥」とも呼ばれます。
植物はまず茎が大きくなり、そこから枝分かれして葉が育ちます。
葉が育てば光合成が活発になり、植物の新陳代謝も捗ります。
このように植物をしっかり育てるためにはチッソが欠かせません。
チッソ不足は植物の生育全体に影響を与えます。
チッソが足りないと茎や葉が大きくならず、その分実をつけるのが遅くなったりします。
特にキャベツや白菜といった葉が成長しないといけない作物では影響を受けやすいです。
葉の全体が黄色くなったりするので、目印・目安にしましょう
チッソは「家畜フン」や「生ゴミ堆肥」などに特に多く含まれています。
落葉などを利用した「腐葉土」などにはあまり含まれていないので注意を。
化学肥料なら「硫安」「塩安」「硝安」「尿素」「石灰チッソ」があります。
尿素は線分が強すぎるので水で薄めて使いましょう。
※石灰チッソは毒性があります。使うときはマスクを忘れずに!
2番目に大切な栄養素
三要素に次いで重要とされるのが「二次要素」と呼ばれる「カルシウム」「マグネシウム」「硫黄」です。
これらの栄養素は三要素の吸収やその成長を手助けをしてくれます。
| 役割 | |
|---|---|
| カルシウム | 細胞壁を強くする |
| マグネシウム | リン酸の吸収の補助 |
| 硫黄 | 根の成長の補助 |
直接的な成長には関わりませんが、あれば生育を良くしてくれるます。
特に栄養がたくさん必要な作物の栽培では重要になってきます。
カルシウム(Ca)
牛乳でおなじみのカルシウム。
元素記号は「Ca」です。
役割も人の場合と同じで植物の身体を強く丈夫にしてくれます。
カルシウムが摂れていれば茎や葉・果実が丈夫になり、しっかりと成長してくれます。
チッソの役割と似ていますが、チッソは「茎や葉を大きくする」栄養素。
カルシウムは「大きくなった茎や葉の細胞壁を強くする」栄養素です。
細胞壁が強くなることにより、茎や葉が固くなり傷つきにくくなります。
逆にカルシウムが足りないと、ちょっとしたことで茎や葉が傷みやすくなります。
白菜やキャベツといった葉物野菜では芯の部分の「芯腐れ」。
トマトなどでは尻の部分の「尻腐れ」など、傷むことが原因で起きる症状が出やすくなります。
新しい葉や根が育たなくもなるため、葉の端が枯れやすくなります。
カルシウムは石灰資材に多く含まれています。
が、撒きすぎによる土壌の「アルカリ化」に気をつけて下さい。
マグネシウム(Mg)
マグネシウムは先ほど紹介した「リン酸」の吸収に必要な栄養素です。
元素記号は「Mg」になります。
たとえリン酸が多く土に含まれていても、マグネシウムが足りないと吸収できません。
そうなるとリン酸が不足したときのように実のつきが悪くなります。
リン酸を充分に与えているのに実が育たないならマグネシウム不足が疑われます。
マグネシウムが不足すると植物の下のほうの葉(新芽の頃に育った葉)が落葉しやすくなります。
そういった書状が出たらマグネシウムを与えてみましょう。
マグネシウムは石灰資材の「苦土(くど)石灰」に含まれています。
苦土石灰にはカルシウムも含まれているので、一緒に補給してしまいましょう。
硫黄(S)
硫黄は根の生育を助けてくれる栄養素です。
元素記号は「S」です。
ただ、硫黄だけあっても根は育ちません。
根の成長に必要な材料は「カリウム」で、硫黄は根の成長を助ける「ブースト」の役割です。
他にも植物に必要な「タンパク質」の合成にも必要になります。
硫黄が足りなくなると根の張りの勢いが衰え、樹勢が強いのに倒れやすくなります。
全体の葉の色が薄くなったりと、チッソが足りないときと似たような症状が出ます。
ただ通常土の中には硫黄が充分量が含まれているので、不足の心配はあまりありません。
肥料では単品では危ないためか、硫黄としてはなかなか販売していません。
しかし肥料の成分で「硫酸~」となっているものは硫黄を含んでます。
心配なら、そういった化学肥料を使えば同時に補給されます。
生育の補助をしてくれる栄養素
ここからは「微量要素」の紹介をします。
メインとして活躍するわけではありませんが、細かいところで使われる栄養です。
| 役割 | |
|---|---|
| 塩素 | 光合成 |
| ホウ素 | 根・新芽・花の生育 |
| 鉄 | 葉緑素の生成 |
| マンガン | 葉緑素・ビタミンの生成 |
| 亜鉛 | たんぱく質・でんぷんの合成 |
| 銅 | 呼吸・代謝・病気の抑制 |
| ニッケル | チッソの供給 |
このように植物ができてから活躍するのが微量要素です。
特に光合成(葉緑体)やたんぱく質・でんぷんの生成は必要なもの。
これらができてないとしっかりした作物の成長はできません。
その名の通り「微量」必要な成分なので、しっかり肥料を与えれていれば不足する可能性は低いです。
そのため単品の肥料として取り扱っているものは少ないです。
家畜フン・生ゴミ堆肥などの有機性堆肥や、液体肥料にバランス良く配合してあります。
塩素(Cl)
殺菌作用のあることで有名な塩素ですが、植物の光合成に必要になる栄養素です。
「Cl」が元素記号の表記になります。
塩素が不足していると新芽の段階で葉が黄色くなったり、葉の先端が枯れたりします。
しかし塩素は雨水や水道水に含まれているので、不足する心配はありません。
ホウ素(B)
ホウ素は根や新芽・花の生育に使われる栄養素です。
主に植物の細胞壁の構成や受粉に使われています。
元素記号は「B」になります。
ホウ素はしっかりした細胞を作るのに必要で、不足すると新芽の段階からうまく育たなくなります。
茎などが脆くなり、実の表面が肌荒れのような症状が出てきます。
特にカブや大根・キャベツなどは多く必要です。
足りないと実や芯が傷みやすくなり、黒く変色する箇所が出てきます。
米ぬかを使うとホウ素も供給できるそうです。
ただホウ素は毒性があります。
粉状のホウ素を使うときはマスクをしたりして吸い込まないように注意してください。
鉄(Fe)
人でもおなじみの鉄分です。
元素記号は「Fe」です。
主に光合成を行う葉緑素を作るのに使われます。
鉄が不足すると葉緑素が作れなくなるので、葉が黄色く変色してきます。
この症状は新しく作られる葉に表れるため、古い葉が緑色のままなら鉄不足を疑いましょう。
肥料としては「鉄イオン」に変換した液体状のものがあります。
製品によりますが、これらは水で1000倍などに薄めて使用します。
粉末タイプもありますが、こちらも与えすぎには注意してください。
マンガン(Mn)
マンガンは葉緑素やビタミンの合成に必要になります。
他にもチッソなどの代謝にも使われるため、これが少ないと生育に影響が出ます。
「Mn」が元素記号。
マンガンが不足したときの症状は鉄不足に似ており、新葉が緑にならず黄色くなってしまいます。
古い葉は緑のままです。
肥料では「硫酸マンガン」という名で粉末状にして販売されています。
亜鉛(Zn)
亜鉛は植物のタンパク質やでんぷんなどの合成に使われます。
他にも光合成の際、二酸化炭素を酸素と炭素に分けるための「酸化還元反応」にも必要になります。
元素記号は「Zn」。
亜鉛が不足すると植物の生育が悪くなり、丈が伸びなかったり葉が大きくなりません。
特にトウモロコシといった穀物類の作物は不足しやすく、なかなか大きくならなくなります。
しかし亜鉛単品の肥料としてはあまり目にしません。
液体肥料などの、他の栄養素と一緒に与えてしまいましょう。
胴(Cu)
胴は植物の呼吸や炭水化物・タンパク質の代謝、病原菌の殺菌に使われたりします。
胴が足りなくなると葉や枝がうまく育たなず、縮んだような状態になります。
他にも実の成熟が悪くなったりします。
亜鉛と同じく単品の肥料としては扱ってないようです。
他の栄養が配合された肥料を使いましょう。
モリブデン(Mo)
あまり聞き慣れない栄養素のモリブデンですが、植物にチッソを供給する大事な役割があります。
元素記号表記は「Mo」になります。
植物がチッソを吸収するためには、チッソ化合物をチッソに分解しないといけません。
この工程を「硝酸還元」といい、このためにモリブデンが必要になります。
モリブデンが不足するとチッソがうまく吸収されず、生育が悪くなったり葉の形がおかしくなります。
亜鉛・胴と同じく、複数の栄養とともに配合されて肥料にされています。
ニッケル(Ni)
ニッケルは尿素をアンモニアなどに分解するのに使われます。
そのアンモニア(NH4)はチッソの材料になります。
「Ni」と表記されたりもします。
ニッケルが不足すると毒性のある尿素が分解できす、葉が枯れやすくなります。
ただ必要量はかなり少ないので、通常の土壌ではあまり不足しません。
こちらも単品の肥料は無いので、液体肥料などで補給しましょう。
土1kgに対する必要量
いろいろ植物の生育に必要な栄養素を紹介しましたが、「じゃあどれくらい必要なの?」と思うでしょう。
そこで土1kgにどれくらい各栄養素が含まれていればいいか表にしてみました。
| 栄養素 | 必要量(mg) |
|---|---|
| チッソ(N) | 30 |
| リン(P) | 3.5 |
| カリウム(K) | 1 |
| カルシウム(Ca) | 1.3 |
| マグネシウム(Mg) | 0.6 |
| 硫黄(S) | 4.9 |
| 鉄(Fe) | 0.004 |
| マンガン(Mn) | 0.74 |
| 胴(Cu) | 0.7 |
| 亜鉛(Zn) | 3.2 |
| ホウ素(B) | 5 |
| モリブデン(Mo) | 0.5 |
| 塩素(Cl) | 20 |
| ニッケル(Ni) | 0.05 |
大抵の作物はこれくらいを基準にした量が土に含まれていれば順調に育ってくれます。
ただトウモロコシやナスといった大き目の野菜などはこれよりも多く必要になります。
特にリン酸・カルシウム・マグネシウムなどは実を大きくするのに多く必要です。
追肥などでしっかり補給しましょう。
ただ大抵の栄養素は雨などで流されてしまうことが多いです。
特にマグネシウムは水に溶けて流れやすく、不足する可能性が他の栄養素より多いです。
マグネシウムはリン酸の吸収を助ける栄養素なので、作物を多く収穫したいならマグネシウム不足にも気をつけましょう。
土壌の栄養素の量は「みどりくん」で調べる
土に含まれていないといけない栄養素の量がわかっても、「じゃあどれくらい土に混じってるんだ?」となりますよね。
そんなときは「みどりくん」という土壌診断キットを使いましょう。
使い方はリトマス試験紙と似ていて、土から染み出た水を試験紙につけて反応を見ます。
反応すると試験紙の色が変わるので、その色の濃度から栄養がどれくらい含まれているのか分かります。
ただ計れるのが「リン酸」「チッソ」「カリウム」だけなのが残念なところです。
最後に
「リン酸」といった重要な栄養素は知っていても、他の微量必要な栄養素はあまり目にしないと思います。
キチンと追肥しているのに育ちが悪いようなら、三要素以外の栄養素が不足している可能性があります。
必要な栄養素を満遍なく供給できる土づくりをしましょう。