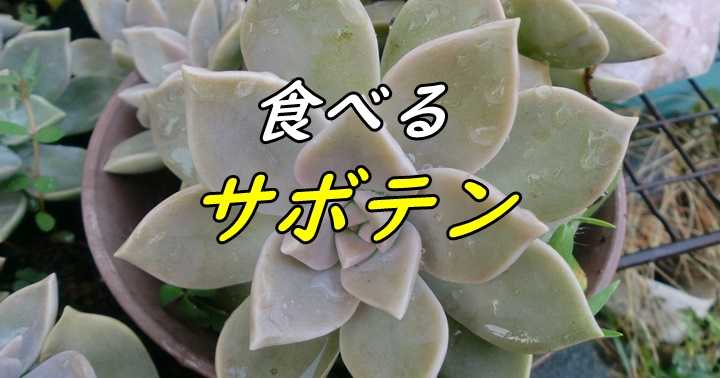自宅でつくるおいしい石焼き芋。甘い焼き芋をつくるためのやり方や必要な道具
冬の風物詩「い~しや~きいも~」でお馴染みの石焼き芋。
…まあ時代なのか、あまり見かけることは少なくなりましたが。
小さい頃に買って食べたときは、よく焼けて甘い芋だったのを覚えています。
…が、今はスーバーなどで買うことがほとんどだと思います。
「できたてのホカホカの焼き芋を食べたい!」という思いのもと、自宅で石焼き芋をやってみました。
※あえて石焼き芋にするメリットも紹介しているので、よければ参考にしてください。
石焼き芋で用意するもの
では石焼き芋をするために必要なものを紹介します。
石

当然ですが石が無いと始まりません。
石焼き芋では石を加熱した際に出る「遠赤外線」を使い、間接的に芋を温める(焼く)ことでつくります。
石焼き芋用の石も販売されていますが、そこら辺に転がってる石でも代用できます。
しかし拾った石の場合は注意したいところがいくつかあります。
・形状
・しっかり洗う
以下のように。最低限は満たしておきたい石の条件があります。
大きさは1.5~3cm
やってみた感想としては石のサイズは1.5cm~3cmで収めたほうがいいです。
大きすぎると隙間が多くなって加熱箇所にムラができます。
逆に小さすぎると焼けて柔らかくなった芋にめり込みやすくなります。
大体このくらいのサイズが扱いやすく、加熱も隙間なく安定してできました。
突起がない石
石にとがった部分や角ばった部分があると、芋に突き刺さりやすいです。
芋が焼けてくると、かなり柔らかくなってきます。
ある程度丸みがあり少々平べったい石のほうが、刺さったりせずに焼けます。
そこらへんから石を拾おうと思っている人は、特にこの部分に注意しましょう。
川辺や海といった場所なら、この条件に合った石を拾いやすいです。
種類はなんでもいい
はっきりいって石の種類はなんでも良く、加熱しても割れないくらいの固さの石ならOKです。
石の採取が面倒なら、ホームセンターの園芸品売り場で「玉砂利」という石が売っています。
この石が石焼き芋で使える条件に一致しやすいです。
ネットショップなどの通販サイトでは、石焼き芋専用の石も販売しています。
「石焼き芋らしい石」が欲しいなら「黒玉砂利」とがイメージ通りかと。
まさしく石焼き芋で使っているあの石がヒットするので、こだわりがある人なら調べてみましょう。
また石の量としては1kg、多くても2~3kgあれば充分です。
あまり多く買いすぎないようにしましょう。
しっかり洗う・乾燥させる
拾った石にしろ、購入した石にしろ、使う前にしっかり洗いましょう。
特に最初に使う場合、しっかり洗ってないと石の土汚れが鍋や芋につきます。
土鍋

石焼き芋では土鍋を使うとうまくいきやすいです。
土鍋は加熱後の保温がしやすく、弱火で加熱しても充分に焼き芋ができます。
また「石」焼き芋の通り鍋の中に石を多く入れるため、石の重さに耐えるだけの耐久性も必要です。
アルミや鉄・ステンレスの鍋などでもできますが、金属製の鍋だと傷がつきやすく劣化も早いです。
特にアルミといった耐久性の低い鍋だと穴が空く可能性もあります。
土鍋ならそういった劣化も少ないので、長く使い続けることが可能です。
大きさは最低でも内側の直径が20cm以上、深さ10cm以上のものがいいです。
石+芋の高さなので、それくらいの大きさでないと鍋蓋が閉めらず、蓋の裏に芋が接触することがあります。
3個以上の芋を一度に焼きたいなら、直径が30cm以上の鍋ならなんとか入ります。
あと使うならもう使わなくなった・捨てる予定のものを使いましょう。
いくら耐久性があるといっても、石によって少なからず傷はつきます。
他の料理と兼用するより石焼き芋専用の鍋を用意したほうが無難です。
石焼き芋専用の土鍋なども売っているので、新しく用意しようと思っている人はどうぞ。
方法①:一気に焼く
石焼き芋をつくる方法ですが、「一気に焼く方法」と「予熱でじっくり焼く」方法の2つがあります。
まずは「一気に焼く方法」から紹介します。
①鍋に石を敷く

まずは用意した鍋などに石を敷き詰めます。
ここがうまくいってないと総合的な焼ける時間が伸びるので注意しましょう。
石の敷き詰め具合は1~2段ほどで鍋の底が隠れるくらいでも充分です。
むしろ石が多すぎると熱が伝わりにくく、加熱時間が伸びてしまいます。
入れた芋がしっかり石の上に置けるくらいの量で充分です。
②芋を入れる
石を入れたら本命の芋を入れます。
芋は上に重ねて入れずに、石に直接触れているようにしましょう。
ふかし芋のように何段も積み重ねても、上の芋には熱が届かずしっかり焼けません。
また一気に焼く場合は、スーパーの石焼き芋のように芋が埋まるまで石を入れないほうがいいです。
あれは加熱器が周囲全体から加熱できる仕組みだからこそできる方法。
家庭のコンロで再現は難しいです。
芋のまわりに石を入れても熱が伝わりにくくなったり、芋をひっくり返すときにかえって面倒です。
もし石を芋の隙間に入れるなら、図のように芋の半分くらいまでにしましょう。
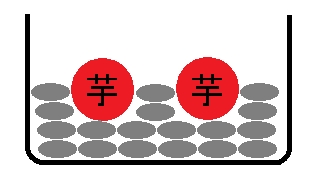
これでも芋をひっくり返すとき少々面倒なので、好きな方法を選んでください。
ただし後述するアルミホイルを使った方法なら、埋めてしまったほうがかえってうまくいきやすいです。
③65℃前後まで加熱
おいしい焼き芋にするには65℃前後の温度が最適といわれています。
芋の甘さは、でんぷんが糖質に変わることで生まれます。
このために65℃前後の温度を維持し続ける必要があります。
この温度より低いと固いままの芋になり、逆に高すぎるとパサパサの焼き芋になってしまいます。
耐熱性の温度計を使うと判断がしやすいです。
芋を入れて中火で10~20分ほど焼いたら、どの程度の温度か確認しましょう。

このくらいの弱火でも充分焼き芋をつくることができました。
鍋の大きさにもよりますが、入れられる芋は詰めても最大4~5本くらいが限界でしょう。
灯油ストーブの上に鍋を乗せてすることもできます。
が、焼き芋の臭いが出るのでその点は考慮してください。
④一定時間で芋をひっくり返す
時間が経ったら芋をひっくり返して他の部分も加熱しましょう。
一気に焼く方法では、短時間では石に接している面しかまともに焼けません。
火を点けて20~30分したら、あとは10~15分毎に芋をひっくり返します。
※芋や石はかなり熱いので、火傷に注意。
軍手のようなものをつけるか、トングなどで芋をひっくり返すほうが安全です。
⑤焼け具合の確認

菜箸や串でうまく刺さる・貫通するくらいが目安。
芋の中心部まで刺されば、しっかり焼けている証拠です。
芋の皮が乾燥して浮いたような状態でも、中まで加熱されていることが多いです。
たまに芋から液体が出ますが、それは芋の糖分が濃縮されたもの。
これが出ているとかなり甘く柔らかい部分ができていることが多いです。
⑥1時間くらい続けたら完成!

④~⑤を続けて、早ければ40分~1時間ほどで石焼き芋は完成です。
もちろん芋が小さければもっと早いですし、大きいともう少し加熱する必要があります。
20cm前後の大きさの芋ならこのくらいで焼けます。
ので、少し時間を確保して石焼き芋をしましょう。
方法②:じっくり焼く
「光熱費を減らしたい」「今すぐ食べるわけじゃない」なんて人は、予熱を使った石焼き芋をしてみましょう。
この方法では「焼いている最中の作業を無くす」「芋全体に満遍なく熱を通す」ことを念頭に置いた焼き方になります。
方法①の「一気に焼く」のと同じ部分はありますが、要所で違う部分があるので気を付けてください。
①石を敷き詰める
「一気に焼く」と同じで鍋底に薄く石を敷き詰めます。
②芋にアルミホイルを巻く

予熱で焼く場合はアルミホイルを巻くとうまくいきます。
アルミホイルを巻けば保温がしやすく、長時間火を点けなくても石焼き芋ができやすいです。
…というよりは予熱を使った焼き方ではアルミホイルを巻かないとうまくいかないことが多いです。
安物のアルミホイルで良いので用意しておきましょう。
③石で埋める
こちらでは芋が埋まるくらい石を入れましょう。
「一気に焼く」方法と違い、予熱で焼く場合はできるだけ熱を逃がさない必要があります。
こうすることで数時間でも熱が籠るようになるので、じっくりと芋を加熱し続けることが可能です。
温度を一定に保ちやすいため蜜化した焼き芋にしやすくなるのも特徴です。
④20~30分加熱
予熱で焼く場合は、入れた石全体が加熱されれば充分になります。
20~30分ほど加熱し続ければ全体に熱が行き渡ります。
できれば上部の石の温度が65℃を超えるくらいは加熱しておきたいところです。
調理用の温度計があると温度の把握がしやすいので、持っていない人は用意しておくと便利です。
⑤1~2時間放置
2時間ほど放置すれば芋全体に満遍なく熱が通るので、蜜状になった石焼き芋になっています。
ただ芋が大きすぎると芋の中心まで蜜化していないことがあります。
もしそうなっていたら再度加熱→1時間放置すれば中までしっかり焼けます。
どっちの方法が最適?
今回「一気に焼く」と「予熱で焼く」の2通りの方法を紹介しましたが、どちらでも石焼き芋はしっかりできます。
ただ成功率やでき方に多少の違いが出ます。
一気に焼く
・焼け具合の確認がしやすい
・蜜化しにくい
一気に焼く方法では作業時間も少なく、どの程度焼けたかの確認もしやすくなってます。
そのため石焼き芋に慣れていない人でも失敗しにくく、調理中の軌道修正もしやすいです。
しかし火をずっと点けているため離れられませんし、高温になるため蜜状の焼き芋ではなくフカフカな焼き芋になりやすいです。
予熱で焼く
・蜜化しやすい
・焼け具合の確認がしにくい
予熱で焼く場合は温度を一定に保ちやすいため、蜜状になった焼き芋にしやすいです。
しっとりして甘い石焼き芋ならこちらのほうがつくりやすいです。
ただ調理時間が長くなりますし、何よりうまく焼けたかの確認がしにくいです。
調理に慣れていないと食べる直前で火が通っていない、なんてことも。
大きい芋だとこれが顕著なので、ある程度石焼き芋に慣れてからやってみるといいでしょう。
なぜ石焼芋なのか?
芋を使った単純な料理(?)には「ふかし芋」や「焼き芋」などがありますが、なぜ石焼き芋をしようと思ったのか?
味や手間の削減といったメリットがあるのが石焼き芋の特徴です。
甘い芋ができる
石焼き芋では甘い焼き芋がつくりやすいです。
石焼き芋でできた焼き芋ではしっかり加熱でき、余計な水分が少ない芋が出来上がります。
わかりやすいのが蜜ができるという点。
焼き芋の表面から出てくるドロドロした液体は、糖質が液状に変化したものです。
蒸かし芋では蒸気のせいで、常時水分が供給されている状態です。
そのため蜜ができても、水で薄まったり流されてしまうことが多いです。
焼き芋では芋の内部に蜜が留まりやく、蒸かし芋に比べて甘さが増しやすいです。
焦げにくい
長時間加熱しても焦げることがないのがポイントです。
直接火で焼くとアルミホイルなどを幾重に巻いても高温すぎて焦げやすいです。
ちなみに火の温度は高いと1000℃を軽く超えます。
しかし焼いた石なら精々数百度と、火に比べ低温ながら調理するには充分な温度。
芋を蜜化させる65℃にするにも、これは重要なポイントです。
このため芋を焦がすことなく、中まで加熱することができます。
極論「ある程度放置できる」ため、精々火元の確認で同じ部屋にいれば充分だったりします。
甘さが持続
焼き芋でできた蜜といった甘い部分は、冷蔵しても日を跨いでも甘さが持続します。
蜜といった部分は完全に砂糖に変化した状態なので、時間が経っても甘さが劣化しにくいです。
もう一度レンジでチンすれば焼きたての芋を味わうことができます。
一度に何本も焼き芋をつくっても、何日かに分けておいしく食べることが可能です。
実際市販される焼き芋では、焼いてから数日冷蔵しているものもあるそうです。
他の調理法との違い
ふかし芋の場合
ふかし芋は熱い蒸気で芋を加熱するため、自然と芋の中の水分量が多くなります。
これがマズいです。
水分が多くいとどうしても甘さが薄くなり、イマイチな感じになりやすいです。
「思ったより甘くない」「何度やっても、どうしても甘くならない」と感じる人はこれが原因でもあります。
キッチンが湯気ですごいことになるので、家中に湿気をばらまきたくない人にとってはここら辺も遠慮するかと。
七輪の場合
焼き芋に次いで甘い芋をつくりやすいのが、七輪の炭火焼を使った焼き芋です。
炭火焼でも遠赤外線を発するため、石焼き芋と同じようにつくることができます。
ただし焼けた炭を使うため温度調整がしにくいという点があります。
焼けた炭が多すぎれば温度が上がりすぎ、少ないと充分な温度になりません。
炭が燃え尽きてしまえば新たに足さなければいけないと手間があります。
一定の温度に保つことが難しいため、それなりに慣れて要領を掴まないと安定して焼き芋ができません。
高温になりやすいためアルミホイルや濡れた新聞紙が必須と、必要なものも増えるます。
焼き芋の場合
焚火でする焼き芋は火加減や時間の調整がかなり難しく、焦がしてしまった人も多いはず。
直接火で加熱するため、どんなに頑張って調整しても芋を焦がしやすいです。
昔は気軽にできた焚火も、今では法律で禁止される場合も多いです。
鍋に石を入れずに直接芋を入れる方法でも、直火に近い温度で焼くのでやはり焦げる可能性は出てきます。
石焼き芋同様に甘い芋はつくれますが、調理に慣れてないと少々難しいと思います。
最後に
これで石焼き芋の調理法+αの紹介を終わります。
やはり石焼き芋でポイントなのは「調理が簡単」なのと「芋の甘さ」になります。
一般家庭で甘い焼き芋をつくりたいなら石焼き芋がお手軽です。
甘い芋や昔ながらの石焼き芋を食べたい人は、ぜひこの方法で石焼き芋をつくってみましょう。