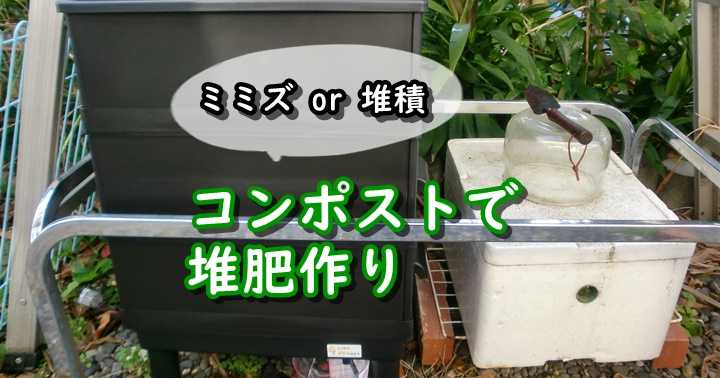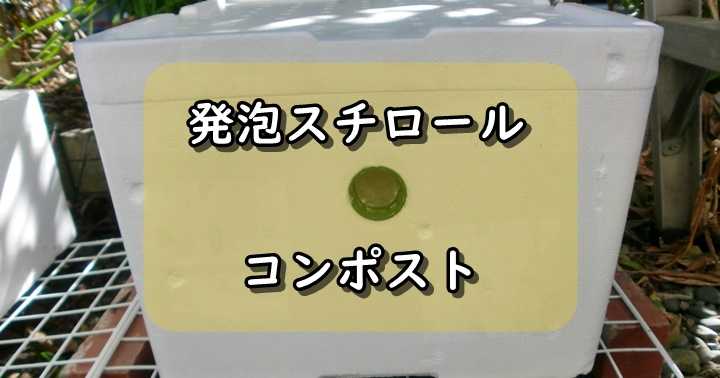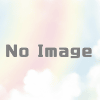コンポストで堆肥を上手につくるコツ。早く生ゴミを分解するのに最適な方法
生ゴミを堆肥にするには「堆積型コンポスト」と「ミミズコンポスト」の2種類があります。
しかし、どちらも最初は微生物が生ゴミを分解しないと始まりません。
微生物は気温や生ゴミの状態によって分解される速度が変わります。
そのため、生ゴミを早く分解するには最適な環境を整える必要があります。
そこで堆肥をつくるのに適した季節やコツを紹介したいと思います。
堆肥作りの時期
夏場前後は出来が早い
春先~秋くらいの気温が高い時期だと堆肥が早くできるようになります。
これは微生物が25℃~40℃くらいの温度で活動するため。
特に生ゴミを入れるだけの堆積型コンポストでは、微生物の分解をメインにして堆肥を作ります。
そのため微生物が活動できる温度設定は重要になります。
ミミズコンポストでも、最初は微生物が生ゴミを柔らかくしないとミミズが食べてくれません。
つまり微生物が活発になれば早く堆肥が作られ、活動が鈍ると遅くなります。
最適な環境なら、堆積型コンポストなら1~2か月くらいで。
ミミズコンポストなら1~2週間ほどで堆肥が出来上がります。
住んでいる地域にもよりますが、大体7月~10月くらいが最も堆肥が早くできる時期になります。
欠点として、この時期は虫が湧きやすいです。
特にハエやコバエ、場所によっては小さなアリが居座ることもあります。
よほど徹底した防虫対策をしていないと、これのせいで堆肥づくりを失敗してしまうことが多いです。
特に堆積型コンポストでは堆肥に変わるまでの時間が長く、虫が湧く可能性も高いです。
そのため防虫ネット(不織布)を使う・臭いを抑えるなどの対策が必須です。
ミミズコンポストなら虫が湧く前に食べきってしまうことが多いです。
虫による失敗を少なくしたいなら、ミミズコンポストを選びましょう。
虫がイヤなら冬場
「虫が嫌なら虫が出ない時期につくればいい」という簡単かつ確実な方法です。
ハエは春先の7~10月に間に活動・繁殖するため、堆肥づくりに最適な時期と完全に被っています。
しかし気温が20℃以下といった低めの気温なら活動しなくなります。
この時期に合わせて堆肥づくりを開始すれば、虫が湧く可能性を低くできます。
ただ時間がかかったり、水分多量になることが多くなります。
微生物やミミズの活動もかなり鈍ってくるので、堆肥に変わるのも遅くなります。
また一番注意したいのが、コンポスト内の水分管理。
冬場は水分が蒸発しないため、生ゴミの水分がコンポスト内に溜まりやすいです。
ビシャビシャになると堆肥作りの邪魔になります。
この時期は水切りされた生ゴミを入れていきたいところです。
堆肥になりやすい・なりにくい生ゴミ
生ゴミにも堆肥になる・ならないものがあります。
よく選んでコンポストに投入しましょう。
堆肥になりやすい生ゴミ
・柔らかい
こうした特徴の生ゴミでは、堆肥に変わるのも早いです。
理由は微生物が生ゴミを分解し(食べ)やすいため。
堆積型にせよミミズにせよ、まずは生ゴミが腐らないと堆肥にはなりません。
そのため、できるだけ腐りやすい生ゴミのほうが堆肥には向いています。
水分が多い生ゴミ
水分を含んでいる生ゴミほど堆肥に変わりやすいです。
これは水分によって生ゴミが腐りやすくなるため。
水分は微生物が活動するのに欠かせません。
また、コンポスト内が乾燥すると微生物やミミズの活動が鈍ってきます。
そのためコンポスト内の湿気を維持するのにも役立ちます。
…まあ寧ろ「水分が多すぎる」という問題の方が多くなりやすいですが…。
果肉・柔らかいもの
果肉などの柔らかい生ゴミも堆肥に変わりやすいです。
これも微生物が食べてくれやすいため。
特にミミズだと、腐るのを待たずに群がって食べてます。
あるいは、加熱されて柔らかくなったものなども同様です。
ただリンゴの芯の部分など、少々固いと腐るのを待つしかありません。
果肉部分はほとんどの果物で食べてくれます。
堆肥になりにくい生ゴミ
堆肥になりにくい、あるいは入れない方が良い生ゴミもあります。
・新鮮すぎる
・キノコの菌床部分
・肉類
・農薬付き
固い皮のようなもの
水分が少ない生ゴミは腐るのが遅く、ミミズがなかなか食べてくれません。
特にジャガイモなどの皮は1ヶ月経ってもなかなか腐らず、腐るまで放置されてました。
キャベツ芯のような、水分はあれど固い部分も同様です。
新鮮すぎる野菜
意外なのがキャベツの葉も腐るのに時間がかかりました。
特に、まだ青々とした新鮮な野菜。
コンポストに投入しても1週間くらいは青々としています。
これは葉の細胞自体はまだ生きているのが理由。
腐るのは細胞が死んでいないと行われません。
キャベツやレタスの外側の葉は捨てがちですが、そのまま入れてもなかなか腐りません。
土を被せても同様なので、こちらもミミズが食べやすくする工夫が必要です。
キノコ(の菌床)
キノコの根元(菌床)部分だと、キノコが生えてくることがあります。
これも新鮮な野菜と同じで、キノコ自体はまだ生きているため。
こちらも日に当てて乾燥させれば、キノコは生えてこなくなります。
大根のヘタやタマネギの根
ニンジンや大根・ホウレンソウといった野菜のヘタ部分。
あるいはタマネギの根がついた部分などは腐りにくいです。
それどころかコンポスト内の水分を吸って成長してしまいます。
決して新鮮な状態でコンポストに入れないようにしましょう。
肉類といった油っこいもの
肉類も腐ってくれば堆肥には変わります。
が、食べきるまでの間に異臭が発生しやすいです。
油分が多いと、微生物が分解してくれるのが遅くなります。
そのため時間がかかっている間に虫が出やすくなります。
これはミミズコンポストでも似たようなものです。
極少量なら何とかなるでしょうが、失敗の可能性を考えるとオススメしません。
農薬・ワックス
ミカンやバナナの皮のようにワックスや農薬がついていそうなものは控えましょう。
特に輸入された果物では皮に何がついているかわかりません。
生ゴミに農薬がついていると、堆肥にも当然農薬が混ざります。
その堆肥で野菜を育てると、最終的に自分が食べることになるのでオススメしません。
ただ、花などを育てている人ならあまり心配いりません。
自家栽培などで「絶対に農薬がついていない」と断言できるものならOK。
じゃんじゃん与えましょう。
堆肥を早くつくるコツ
ここからは微生物がより早く分解できるように工夫する方法を紹介します。
これらの方法を取ると1~2週間は堆肥つくりを短縮できます。
虫沸きによる失敗などの予防にもなります。
土を被せる
単純ですが、土を被せれば分解も早く進みます。
土が生ゴミに接触すれば微生物やミミズが食べやすくもなり、処理スピードも上がります。
ただ注意したいのが一か所にまとめて埋めると、内側の生ゴミの腐るスピードが遅くなります。
ある程度小分けにして埋めるか、少し土を混ぜ込むようにして埋めると良いでしょう。
土を被せるだけでもかなり効果はあります。
少々手間ですが、早く生ゴミを処理するならやってみましょう。
発酵促進材を入れる
発酵促進材を生ゴミと一緒に入れると分解が早くなります。
発酵促進材とは微生物の活動を活発にして、堆肥を早く作れるよう促せるものです。
代表的なのがトウモロコシの粉末・米ぬかなど。
これらを生ゴミに撒く・混ぜ込むと生ゴミの微生物の活動が活発になります。
また発酵が進むとコンポスト内の温度も上がるため、寒い時期でも堆肥作りがをしやすくなります。
促進剤自体も堆肥の材料になるので安心して使えます。
注意点が「大量に入れすぎる」こと。
発酵促進材を大量に生ゴミに混ぜると、アンモニアが大量に発生します。
異臭の原因になったり、ハエが引き寄せられたりと失敗する恐れがあります。
また発酵促進剤の粉末が水分を吸ってダマになったり、固まったりします。
塊になるとより分解しにくくなります。
大量に使うなら臭いが漏れないよう密閉する・中の空気を抜く必要があります。
効果は高いですが、取り扱いには注意して下さい。
電子レンジで加熱する
電子レンジで加熱すると生ゴミの細胞が壊れ、腐りやすくなります。
食品を加熱すると細胞が破裂して壊れます。
この「壊れる」というのは「柔らかくなる」ということ。
人参などの固い野菜がフライパンなどで炒めると柔らかくなるのはこのため。
レンジならダイレクトに細胞を壊せるので、短時間で生ゴミを柔らかくできます。
分解時間が半分以下になることも多いです。
生ゴミが出てから早くに堆肥に変えたいときに使える方法です。
冷凍する
電子レンジと同じく生ゴミを冷凍すると細胞が壊れ腐りやすくなります。
これは生ゴミの細胞の水分が凍って膨張して破裂するため。
水の入ったペットボトルを凍らせるとパンパンに膨らんでますよね?
細胞もそれと同じ状態になっていますが、ペットボトルほど固くないので破裂してしまいます。
ちなみに肉を解凍した後に出る汁は、肉の細胞が壊れて漏れ出たもの。
低温で徐々に凍ると効果も高いため、「急速冷凍」以外の冷凍庫で凍らせましょう。
生ゴミの保存にも使えます。
一度に大量の生ゴミが出たら、後日与えるために冷凍してみましょう。
乾燥させる
キャベツの葉のような新鮮なままの野菜。
あるいは水分が多すぎるなら、ある程度乾燥させましょう。
生ゴミが新鮮でまだ細胞が生きている状態だとなかなか腐りません。
しかし、少し乾燥させて弱らせると腐りやすくなります。
それに生ゴミの水分が多すぎると、コンポスト内がビシャビシャになる原因にも。
1~2日ほど乾燥させれば充分です。
そういった生ゴミが多いならすぐに投入するのは控えましょう。
生ゴミを細かく切る
生ゴミを細かく切れば隙間も無くなり、微生物が活動しやすくもなります。
生ゴミの表面積も増えるため、発酵の速度が上がったり微生物が住み着けるスペースも増えます。
特にキャベツの芯や大根・人参といった固いものほど分解が遅いです。
できれば1cmくらいの大きさに切っておくと分解も早くなります。
生ゴミを押し込む
生ゴミを押し込むことによって隙間を無くしましょう。
理由は上記で説明した通り「入れられる量を増やす」「微生物が活動しやすくする」ため。
隙間があると微生物やミミズが活動しにくなります。
生ゴミや土を密着させるようにしましょう。
排水は頻繁に
きっちり排水することによって、容器内の水が抜けて微生物に適した湿度になります。
そうすれば分解も進み、腐敗も起きにくくなります。
排水しないとあっという間に水が溜まり、生ゴミが徐々に腐敗していきます。
処理しないと。腐敗した生ゴミが排水口に詰まり排水できなくなります。
こまめに排水して、容器の中の水を抜きましょう。
生ゴミ(野菜くず)の分解速度
生ゴミ、特に野菜くずの分解速度の早さになります。
時間はかかりますが、最終的には分解されます。
・切って入れる
・加熱や冷凍加工
これらにジャンル分けしました。
とりあえず生ゴミが出やすいものを中心として書いていきます。
◎…良く食べる。2~3日で食べきる。
○…標準。4~5日ほどで食べきる。
△…少々食べにくい。一週間以上残っていたりする。
×…中々食べない。長いと1ヶ月近く食べないことも。
根野菜
根野菜は軒並み固いものが多いです。
そのため細かく切ったり加熱・冷凍加工しないとなかなか分解されません。
特に皮の部分は水分も少なく固いため、加工しても残ることが多いです。
| そのまま | カット | 加熱or冷凍 | |
|---|---|---|---|
| 人参 | △ | ○ | ◎ |
| 人参の皮 | △ | △ | ○ |
| ジャガイモ | △ | ○ | ○ |
| ジャガイモの皮 | × | × | △ |
| 大根 | △ | ○ | ◎ |
| 大根の皮 | △ | △ | ○ |
| タマネギ | ○ | ◎ | ◎ |
| タマネギの表皮 | × | × | △ |
葉物野菜
葉物野菜は柔らかく水分も多いため、細かくすると早くに腐るものが多いです。
加熱・冷凍するとより分解されやすくなるのも特徴。
ただキャベツの芯など固い部分は、切る・加熱するのが前提で入れましょう。
| そのまま | カット | 加熱or冷凍 | |
|---|---|---|---|
| キャベツ | △ | ○ | ◎ |
| キャベツの芯 | × | △ | ○ |
| レタス | △ | ○ | ◎ |
| レタスの芯 | △ | ○ | ◎ |
| 白菜 | △ | ○ | ◎ |
| 白菜の芯 | △ | ○ | ◎ |
| チンゲン菜 | ○ | ○ | ◎ |
| チンゲン菜の芯 | △ | ○ | ◎ |
| ほうれん草 | ○ | ○ | ◎ |
| ほうれん草の茎 | ○ | ○ | ◎ |
果実系
ナスのような野菜は食べれない部分が生ゴミになるため、少々固いものが多いかと。
ピーマンのように柔らかいものもあるので、種類に応じて加工するかどうか決めましょう。
| そのまま | カット | 加熱or冷凍 | |
|---|---|---|---|
| ナス | × | △ | ○ |
| キュウリ | ○ | ○ | ◎ |
| ピーマン | ○ | ○ | ◎ |
| トウモロコシの芯 | × | × | △ |
果物
果物は柔らかく、水分が多いため早くに腐りやすいです。
ミミズも好んで食べるため、優先して与えたいところ。
ただワックスや農薬がついている可能性のあるものは控えましょう。
また甘い匂いのせいで虫が湧くことも多いです。
土に埋めること前提で入れましょう。
| そのまま | カット | 加熱or冷凍 | |
|---|---|---|---|
| リンゴ | ○ | ○ | ◎ |
| リンゴの皮 | △ | △ | ○ |
| スイカの皮 | ○ | ○ | ◎ |
| メロンの皮 | ○ | ○ | ◎ |
番外1:卵の殻
卵の殻を堆肥にしたいなら細かく砕いて少量だけ与えましょう。
卵の殻はかなり固く、中途半端に砕くと鋭利な部分ができます。
ミミズコンポストだとミミズを傷つけやすくなります。
与えるときはすり鉢などで細かくしてから、少量をふりかける程度に与えましょう。
ただ卵の殻は土壌に直接混ぜ込めるので、あえてコンポストに入れる必要性はあまり無いです。
番外2:野菜や果物の種
野菜や果物から出る種はコンポスト内で発芽する場合があります。
リンゴやミカン・カボチャの種といった種に殻がついているもの。
あるいは新鮮な種。
こうした種はコンポスト内の水分で発芽しやすいです。
カボチャの種を入れて1週間くらいしたら、コンポスト内がカボチャの芽でいっぱいになってました。
せっかく出来た堆肥の栄養を発芽した種に取られるのは業腹です。
生ゴミに混じった種は選別してからコンポストに投入しましょう。
番外3:魚や肉類
魚の皮や肉・油粕といった脂分や臭いが強いものはあまり入れないほうがいいです。
腐る時間こそ早い部類ですが、これらの生ゴミは強い臭いが出ます。
ハエといった害虫を呼び寄せてしまうため、大量に投入するのは控えましょう。
入れるとするならば少量かつ土の奥深くに埋めるようにしましょう。
まとめ
堆肥づくりを経験して最も重要なのが、いかに「虫が湧かない」「水を抜く」かだと思います。
これさえできれば、時間がかかっても確実に堆肥は作れます。
堆肥をつくる方法は個人で多少違いが出るでしょうが、これだけは守って堆肥づくりをしましょう。